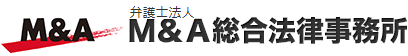事業承継の後継者不足の原因と解決方法を解説

近年、特に中小企業を中心に、後継者不足の問題が深刻化しているという話を耳にすることがよくあります。また、実際に、後継者が見つからず、最終的に事業をやめて、廃業に追い込まれてしまう企業も増えています。
企業が廃業に追い込まれてしまうと、それまでにその企業で蓄積されてきた事業の技術やノウハウが失われることにもなってしまいます。これは、その企業だけでなく、社会にとっても大きな損失です。一体、後継者不足の実態はどのようになっているのでしょうか?また、その原因はどのようなもので、これらの問題についてどのように対処すればよいのでしょうか?
最近では、M&Aなどの手法によって事業承継するといった方法も見られるようになってきています。でも、それなりの知識がないとM&Aといった方法には踏み出せない経営者も多いと思います。
また、日本の財政や技術・経済は企業によって支えられていますが、近年は中小企業を中心に廃業が増加しています。理由としては、後継者不足が目立ち、実際に後継者不在を理由に廃業を検討する経営者も少なくありません。
本稿では、後継者不足の現状や理由に触れたうえで、廃業以外の選択肢についても概観します。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
後継者不足問題とは
後継者不足問題とは「日本の中小企業などにおいて、事業を引き継いでくれる人(後継者)がいないために、その会社の継続が難しい状況になってしまう」という問題です。中小企業などの事業を行う経営者が、会社を一生懸命に発展させたとしても、次の世代の経営者、つまり「後継者」が見つからなければ、せっかく育てた会社や事業を廃業して終わらせなければならなくなります。
日本の会社の99%は中小企業です。一方で、少子高齢化や事業や技術を継いでくれる若者がいなかったり、会社の人材が不足していたりするなどの理由から、日本の会社の99%である中小企業のうち、3分の2(約65%)の会社が後継者問題を抱えていると言われています。つまり、現在の日本の多くの会社が直面する問題が、後継者不足問題だと言えます。
後継者不足の状況
経営者の中でも「リタイアはもう少し先だ」「まだ現役で働ける」という風に考えている人は、後継者不足問題を身近に感じられていないかもしれません。しかし、後継者不足問題は近年の日本においては、かなり深刻な状況になっていると言えます。もっと身近に、そして差し迫った問題であると理解できるようにするために、日本の後継者不足がどのような状況なのか、具体的なデータを示して説明しようと思います。
東京商工リサーチによると、2020年の休廃業・解散・倒産は4万9,698件(調査開始以来の最多)。2019年に一時減少したものの、2020年はコロナ禍の影響等で再び増加しました。注目すべきは「黒字でも廃業」が一定割合で存在する点で、2020年の休廃業・解散企業の61.5%が当期黒字でした。
経済産業省の試算では、現在の日本における後継者不足問題が解決しない場合、2025年頃までに最大約650万人の雇用と約22兆円分のGDP(国内総生産)が喪失するとされています。日本政策金融公庫によれば、60歳以上の事業を行う経営者のうち50%超が将来的な会社の事業の廃業を予定しています。このうち「後継者不足」を理由とする廃業が全体の約3割に迫る勢いとなっています。
中小企業庁の試算では、2025年までに平均引退年齢70歳に到達する経営者が約245万人、うち約127万人が後継者未定とされています。後継者不足が放置されれば、雇用とGDPに重大な影響が及ぶ可能性があります。
このような状況を見てみると、後継者不足はそれぞれの会社の事業存続という点でも大問題ですが、日本の将来的な雇用創出という点でも重大な問題です。後継者の不在によって廃業する会社が増えると、その分だけ将来の若い人たちの働き先がなくなります。
経営者にとって、後継者不足問題は、「自分はまだ現役だから関係ない問題だ」と思っていても、さらに歳を経て、子や孫の代になると、事業や働く場所がないという別の問題を連鎖的に引き起こす可能性が指摘されています。後継者不足は将来的に日本にとって大きなマイナスです。
また、会社が後継者不足によって廃業するということは、その会社が持っている技術や販路、知識、製品も失われるということに他なりません。会社の事業の廃業によって製品や技術が失われた結果、日本全体の技術力の低下や日常生活に関わってくる可能性すらあるのです。
ここで、業種別の後継者不足問題の状況について見ていきたいと思います。産業別の「後継者不在率」は、全国企業「後継者不在率」動向調査(2020)によると、情報通信サービス業が73.1%で高くなっています。
情報通信サービス業の後継者不在率が高い理由としては、ソフトウェア開発などIT関連業種が含まれるため、事業を行っている歴史が浅い企業が多く、代表者の年齢も比較的若いことが影響しているとみられます。
その他の人手不足による影響が深刻な業種は、小売業が66.4%、建設業は70.5%、運輸業は61.3%でした。全産業平均は61.5%で、ほぼ全ての業種で後継者不足が進んでいることが考えられるという結果になっています。
このような業種の事業の廃業が進むと、例えば、情報通信業の廃業が進めば、現状はインターネットなどの情報通信が問題なく使えていますが、近い将来に仕事の根幹になるインターネットやシステムも満足に使えないという事態に陥りかねません。
また、建設業の廃業が進むと、不動産や道路の修繕を急がなくてはならないのに、建設業のスキルや知識、そして会社の絶対数が不足して満足に工事などが進まない可能性があるのです。
さらに、運輸業の後継者が見つからないと、日本各所への物資の輸送が滞り、物流が満足におこなえなくなります。日本中の会社の事業にも差しさわりが出るほか、日常生活も大いに不便になることでしょう。
後継者不足は近い将来の日本の雇用や生活にもつながる重要な問題になっているのです。
このように、日本を支える存在である中小企業が後継者不足問題による衰退が危ぶまれることから、後継者問題への対策が急がれる状況です。
以前であれば、とにかく後継者を探したり、育てたりするしか方法がありませんでしたが、最近では、M&Aによって他の企業に事業承継するという方法も一般的になりつつあります。M&Aのような方法を活用するということも、考慮した上で事業の承継を考えることも一つの選択肢だと言えます。
また、国や地方単位で後継者問題の解決を考えることも重要ですが、会社の経営者自身が「後継者不足問題は身近な問題である。自分にも関係のある問題である」と理解して、早めに対策を取ることも重要であると言えます。
後継者不足の深刻な業界
日本の全体的な課題である後継者不足ですが、後継者不足問題の深刻度は業界によって異なります。特に後継者不足が顕著な業界と、その特徴を解説しようと思います。
建設業
全国企業「後継者不在率」動向調査(2020)によると、最も後継者不在率が高い業界は建設業で、70.5%となっています。後継者はもちろんのこと、若手人材も大きく不足している背景には、建設業ならではの理由があるように思われます。
建設業は、3K(きつい、汚い、危険)のイメージが強く、仕事自体が激務の割に一部の大手ゼネコンなどを除いて給与水準が高くないため、若者に避けられがちであることは否めません。作業員の高齢化も顕著で、55歳以上のベテラン層が35%という非常に高い割合を占める一方、29歳以下は全産業平均を下回る11%と、ミドル世代以上が中心となって人員分布を構成するような環境になっています。
また、さらに後継者不足が深刻な原因としては、現場で働いてきた職人気質の人が多く、単身または家族経営で働く「一人親方」も多いことから、そもそも事業継続・後継者育成への関心が低い傾向があるということが挙げられます。さらに人手不足から企業の建設業許可に必要な有資格者も減少してしまうなど、いくつもの要因が絡み合っているのが現状です。
小売業
小売業の後継者不在率も、全国企業「後継者不在率」動向調査(2020)によると66.4%と高くなっています。そして、それに伴い、後継者が見つからずに廃業になってしまうケースも多くなってきています。
廃業となるのには、さまざまな理由が考えられますが、ひとつには業績の悪化が挙げられます。今後業績が回復する見込みがあればまだしも、そうでない場合には多くの経営者が廃業を視野に入れるでしょう。業績悪化に伴いキャッシュフローが悪化し、経営が回らなくなることは珍しくありません。人手不足も理由として考えられます。
現代は働き手の選択肢が多く、魅力的な労働条件を設定しないとなかなか人材を確保できません。小売業において、人材を確保できないのは大問題です。また、小売店が扱う商品は流行り廃りがあるため、その波に業績が影響されることも少なくありません。流行っているときには恩恵に与れますが、流行が廃れたときはたくさんの在庫を負債として抱えることになってしまいます。
小売業の廃業理由の多くは一般的な中小企業と大きく変わりません。ただ、小売業特有の廃業理由として挙げられるのが、ECサイトの台頭です。現在では多くのECサイトが台頭し、外出せずにパソコンやスマホで買い物できる時代になりました。ECサイトは実店舗が不要なため、低コストで運営でき商品の価格も安くできます。そのため、実店舗経営がメインの小売店にとって、ECサイトの台頭は大変な脅威です。
このような小売業界の現在の状況から、後継者がなかなか見つからないことを理由に、廃業を考えるケースも少なくありません。あとを任せられる人材を育成できていればよいのですが、そう簡単なことではないでしょう。このような場合でも、M&Aによって事業を他の企業に承継してもらうことで、事業継続や雇用継続ができます。
運輸業
運送業界も全国企業「後継者不在率」動向調査(2020)によると61.3%と高くなっています。
運送業界では、インターネット通販の活発化による宅配業の需要が高まりを見せ、人手不足が強く叫ばれるほど活況な状態です。このように運送業界全体としては、業績も順調で問題なく見えます。しかし、運送業界において大多数を占める中小業者間では、活況であるがゆえに過当競争が発生しています。
中小業者の場合、運送業務は二次請け以降の下請け仕事であることがほとんどです。二次どころか三次、四次、五次ということさえあります。下請けの仕事になった場合、利益率がよくないことが通常です。その中で、同業者同士によるサービス競争=価格競争となるため、さらに利益率が低下したり、それゆえに多くの業務を引き受ける結果、ドライバーの業務に負担がかかったりしていきます。
運送業界は参入障壁自体がそれほど高くないこともあり、毎年1,000社ほどの新規参入事業者があります。そして、ほぼ同数の事業者が撤退していくような状況です。運送業界内の過当競争が価格競争となり、会社の利益率を圧迫させることによって資金繰りが悪化するという構図が垣間見えてきます。そして、資金に余裕がないため、本来であれば好条件を提示して確保したい人材も、思うように雇用ができないという悪循環に陥ってしまいます。
その結果、高齢化していく既存ドライバーの長時間労働という問題も生じています。このように、運送業界の全体像としては活況感があるものの、大手企業と中小企業間の経営格差が改善されていかないと、真の業界の好況とは言えない実態が横たわっています。
小さな運輸企業がM&Aで同業他社に事業承継すれば、規模が大きくなることによるメリットを享受できる可能性もあります。
後継者不足の原因
これまで見てきたように、中小企業を中心に、日本全体で企業の後継者不足が深刻な状況となってきています。では、その後継者不足の原因として考えられるのは、どのようなことなのでしょうか?いくつかの主な要因について考えてみたいと思います。
少子化
後継者不足が起こる原因として、少子化による後継者不在が1つの理由となっています。これまで、中小企業の後継者は、多くが子どもへの事業承継で成り立っていました。
しかし、少子化によって、そもそも子ども自体の数が減り、さらに子どもがいたとしても、親が行っている事業を引継ぎたくないと考える子どもも増えたことで、後継者不足が起こり、親族間の事業承継は年々減り続けています。
さらに、日本全体の少子化によって、若い従業員が中小企業に入社してこないといった状況も起こっています。その結果、従業員の誰かに会社の事業を引き継ごうと思っても、引き継ぎを行ってくれる次の経営者候補がそもそもいないという状況に陥ってしまうというようなことも発生してしまっています。
出生数は戦後以降長期的に減少傾向で、年齢別未婚率も上昇しています。子どもの人数が少ないほど親族内承継の可能性は下がり、結果として後継者不在に陥りやすくなります。
親族内での承継がない
前述したとおり、ひと昔前までの日本では、家業は子どもが継ぐものという風潮がありました。しかし、社会的な価値観の多様化や家族のあり方が変化したことによって、中小企業の経営者や個人事業主は、子どもや親戚に後継者を強制することが少なくなり、後継者不足が起きています。
また、親族間の事業承継は相続の問題や個人保証の問題など、さまざまなトラブルが起こる可能性があることも事実です。事業譲渡や株式譲渡などのM&Aによる事業承継の際も、M&Aによって後を継ぐ親族の税負担や資金面の負担を考えて、親族内でのM&A承継をためらうオーナー経営者が多く存在します。
親族間のトラブルや後継者の負担を避けたいという意識が、後継者不足による会社の事業継続が困難な状況をさらに助長する結果となってしまっています。
働き方の多様化等により、親族が会社を継がない事例が増加しています。候補はいても承継意思がない「候補はいるが後継者はいない」状態が多発しています。
経営の先行き不安
日本政策金融公庫が行った事業承継に関するアンケート調査で、廃業予定理由として最も多かったのは、「当初から自分の代でやめようと思っていた」、そして次点が「事業に将来性がない」でした。この2つの理由が全体の65%を占めています。日本国内の消費活動が人口減で縮小していく状況のなか、さらに、テクノロジーの進化により経済トレンドの変化は速くなる一方です。数年先を見通すのも難しい現代で、経営者や後継者候補の親族、従業員は自社の事業の継続性に不安を抱えています。その結果、事業の引継ぎをためらう事態となり、後継者不足に拍車をかける結果に陥っています。
事業承継の準備不足
事業承継の準備期間は、後継者の育成も含めると5年から10年は必要であるとされています。
しかし、帝国データバンクの「中小企業における事業承継に関するアンケート・ヒアリング調査」によると、60歳以上の中小企業経営者のうち約半数が「これから準備をする」「現時点では準備をしていない」「現在は事業承継を考えていない」との回答をしています。
後継者不足を解決するには早めの対策が必要ですが、実際には解決のための対策ができていない経営者が多い現状となっています。経営者が後継者不足への対策ができていない主な理由としては、「日々の経営で精一杯」、「何から始めればよいかわからない」、「誰に相談すればよいかわからない」の3つが主なものとされています。
これらの理由は、経営者の自助努力では解決が難しい面があります。そして、事業後継者対策の遅れが後々の後継者不足につながっています。事業の承継の手段としては、M&Aなどの手法もあるにも関わらず、M&Aに対する知識のない経営者が多くいるというのも事実です。後継者不足に対する対策の遅れを解決するには、国や地方自治体、M&Aの専門家などのサポートで後継者の対策やM&Aの実施のための環境整備が欠かせないと思われます。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
後継者不足問題の対策・解決方法とそれぞれのメリット・デメリット
後継者不足問題を解決して、廃業を免れるためには、どのような対策や方法が考えられるのでしょうか?いくつかの事業承継方法を挙げて、それらのメリット・デメリットを見ることで、それぞれの状況に相応しい解決策が見つかるかもしれません。ここでは、「親族内での承継」、「親族外での承継」、「事業承継M&A」、「IPO」について見ていきたいと思います。
親族内での承継
親族内承継は、先代経営者の子どもや配偶者などの親族を事業の後継者とする方法です。後継者不足を解決する際には、まずは親族内で後継者候補を選定するというのが一般的に思い浮かびます。しかし、親族内承継を成功させるためには、早急な後継者の選定と教育が不可欠になってきます。後継者の教育は、もちろん、後継者となる人の能力によって差がありますが、一般的に5~10年ほどかかるといわれています。
そのため、先代経営者が若い、40~60代のうちに後継者を確定し、いち早く後継者教育を始めることが大切になってきます。具体的な教育方法としては、実際に先代経営者が経営している会社の重役として経営に参画し、経営や実務に必要なノウハウを直接覚えるという方法が一般的です。もしくは、後継者候補の親族を外部の同業他社などに入社させ、そこで会社経営に必要なノウハウを網羅的に習得させるというのも、一つの方法だと思われます。
メリット
親族であれば、条件などの交渉が進めやすく、話がまとまりやすいメリットがあります。また、M&Aの手続きも簡略化できる場合があり、短期間でM&Aを完了することも可能です。
デメリット
親族間の事業承継では、株式の譲渡やM&Aによる事業承継によっても、相続税や贈与税の負担が大きかったり、後継者が事業を買い取る負担が大きかったりと、資金面の問題が起きる可能性があります。
M&Aを含む、事業承継にはさまざまな税務上の特例があるので、うまく活用すれば税負担を抑えることが可能です。しかし、M&Aなどの税制の特例を活用するにはM&A専門家などの協力が欠かせず、時間もかかります。
親族外での承継
親族外承継は、親族以外の役職員に会社を引き継いだり、外部から経営者を招き入れたりする方法のことです。近年は、親族外承継が親族内承継に代わってメジャーな事業承継の方法となりつつあります。
そのような親族外承継で後継者不足に陥らないためには、後継者候補に「会社を引き継ぎたい」と思わせることが重要になってきます。なぜなら、親族以外の人にとって、中小企業を引き継ぐということは、とても大きなリスクのように感じる可能性があるからです。
親族外承継で最も大きな障壁となるのは、自社株の買い取り費用の問題です。自社株の大半を引き継ぐには莫大な費用がかかります。
そのため、例えば無償で自社株を譲渡したり、自社株を購入するための費用を外部の金融機関から融資を受けたりするなどして、なるべく後継者の負担にならないように配慮しなければならなくなります。
また、今後倒産しそうな会社では、誰も後継者の役目を引き受けてくれない可能性が高いため、経営の先行き不安を少しでも解消することも重要となってきます。
そのための手法としては、例えば、自社の強みを強化したり、不採算の事業からは撤退したりするなどの経営を強化する施策が効果的と考えられます。このような経営不安の解消や経営強化においても、知識や経験の豊富なM&A専門家の活用が有効だと思われます。
メリット
後継者候補を選んで教育する方法であれば、自社の業務内容に適性のある人物やリーダーとしての資質がある人物に事業承継できるので、事業を継続、成長させていくことが可能です。
また、自社の理念や経営方針もすでに身に付けているので、企業風土も維持できるでしょう。さらに、後継者候補を教育している間に、従業員や取引先との関係も築けるので円滑な事業承継が期待できます。
また、別の方法としては、外部から経営者候補を招聘するという方法も考えられます。これによると、経営者のスキルと実績を持った人物を招くことで、事業の継続と成長が期待できます。また、新しい経営者の視点から、自社の強みを伸ばし、弱みを改善できる可能性もあるでしょう。
デメリット
後継者候補が複数いる場合は、後継者争いが起きる可能性があります。また、後継者候補を育てるには時間がかかり、身に付けるべきスキルは多岐に渡るため、計画的に後継者教育を行わないと、徒労に終わる可能性も否定できません。
外部から後継者を招く場合は、候補者を見つけて交渉する必要があります。後継者を招くことができ後継者不足は解消されたとしても、経営方針の違う経営者の就任によって、企業風土が変わる可能性があります。また、従来からの従業員との間に確執が生じる恐れがあるということも否めないでしょう。
事業承継M&A
従来、親族や会社内に後継者がいない中小企業は、廃業せざるを得ないことが一般的でした。しかし近年は、M&Aを活用して廃業を回避するケースが増えています。M&Aでは、自社の株式を外部の法人や経営者に譲渡する形でM&A事業承継を行います。外部の幅広い法人・経営者の中から会社の引き継ぎ手を探すため、M&A事業承継は、後継者不足により親族内や社内で事業承継できない企業には最適な手法と言えます。
ただし、後継者不足に陥っているような中小企業の大半は、業績悪化や倒産のリスクが高い傾向にあるため、簡単にはM&Aの相手を見つけられないという一面もあります。後継者不足の企業がM&Aを果たすには、買い手にとってM&Aで買収する価値のある企業にしなくてはなりません。
具体的には、有利子負債や不要な在庫を削減しつつ主力事業を強化し、収益性を伸ばすことでM&Aの買い手にとって魅力的になるように、企業価値を高める必要があります。短期間で企業価値を高めることは実現できるものではないため、M&Aによる事業承継を考える企業は、M&A専門家などの協力を得て、後継者不足を認識した時点から早めに対策を行うことが不可欠になります。
メリット
M&A・事業承継の専門家を介してM&A事業承継候補の企業をさがすのであれば、後継者不足に関する相談先としての信頼性が高く、M&Aに関する信頼できる幅広い情報を持っているので、M&A事業の引継ぎ先として最適な相手を紹介してもらえる可能性が高くなります。
また、M&Aや事業承継の手続きも一貫してサポートしてもらえるため、M&Aによるトラブルや失敗の確率を低く抑えることが可能です。
また、M&Aによる事業承継を用いること自体での主なメリットには、以下の2点があります。1つは「M&Aを行うことによる売却益を得られる」ということ、もう一つは「M&Aによって事業や技術が引き継がれる」ということです。
M&Aによる事業承継では、後継者不足が解決するだけでなく、M&Aによる売却益を得られます。中小企業がM&Aで用いる手法は、主に株式譲渡です。
株式譲渡によるM&Aの売却益には、個人の場合は譲渡所得税、法人の場合は法人税が課税されますが、税引き後でも十分にリタイア生活を送れるだけのM&Aの売却益が得られることもあります。
また、廃業すると長年育ててきた事業や技術が失われてしまいますが、M&Aによる事業承継であれば、貴重な経営資産を残すことができます。
M&Aによる事業承継は、後継者不足が解決されるだけでなく、事業を支えてきた従業員や取引先などの生活も守れるので、経営者にとっては大きな安心材料です。
デメリット
M&Aや事業承継の専門家に依頼した場合、M&A専門家の依頼先によっては、M&Aの仲介手数料が高額になることがあります。M&Aを行うことによる報酬体系にはM&A専門家によって大きな差があるため、M&Aの依頼を検討する際は事前によく確認することが必要です。
また、場合によってはM&A専門家側の都合に合わせた相手を紹介されることもあります。依頼するM&A専門家が誠実に対応してくれるか、よく見極めることが重要です。
M&Aによる事業承継を株式譲渡で行う場合、後継者に債務も引継ぎます。しかし、それだけではなく、M&Aによって後継者に引き継いだ債務の中に簿外債務が隠れている可能性があります。
簿外債務とは、M&Aの実施時期には帳簿上に出てこない隠れた債務を意味します。M&Aの売り手側が意図的に隠している場合もありますが、M&Aの売り手側も気付かないままM&Aが完了してしまうこともあります。
M&Aの売り手側はM&Aの際に自社のリスク要因をしっかりと洗い出し、M&Aの買い手側はデューデリジェンス(DD)(企業監査)を入念に行わなければなりません。
M&Aによる事業承継の成功率は3割~5割ほどともいわれています。M&Aによる譲渡資金などの条件が折り合わず、どちらかが妥協しなければならない場合があります。
M&Aによる事業承継の手続きが無事に済んだとしても、M&A統合後に思ったように事業シナジーが得られなかったり、人材が流出してしまったり、予定以上に多くのコストがかかったりすることもあります。
後継者不足の解決だけでなく、M&Aによる事業承継後の事業継続性、成長性も考慮することがM&A事業承継をする場合には必要となってきます。
IPO
IPOとは、「新規公開:IPO(Initial Public Offering)」ということで、非上場・未公開の企業が株式等を証券取引所(株式市場)に上場(公開)させることをいいます。株式公開に際しては、通常、新規資金を調達するために発行した新株や、既存の株主が保有している株式などの売却が行われます。これにより広く一般の投資家がその企業の株式を保有することができ、証券取引所で自由に売買ができるようになります。
IPOを目指す場合には、数年前からIPOのための準備を行う必要がありますが、大切なことは事業の成長性です。IPOにより、一般の投資家から広く資金調達し、その資金でより成長を加速させていかなければなりません。また、東証プライム、スタンダード、グロースと市場がありますが、それぞれ上場審査基準が細かく定められています。
例えばグロースであれば、流通時価総額5億円以上が必要であるため、企業価値評価が低い場合は審査基準を超えるために事業規模を拡大しなければなりません。また、IPOをすることによって、会社が世の中に広く認知されるようになるため、後継者候補となり得る優秀な人材が集まったり、M&Aの候補会社が見つかったりするなど、後継者不足を解消できる可能性がありますが、直接的な事業継続の解決策とはなり得ません。
メリット
IPOのメリットは次のようなことが考えられます。「IPO時に保有株を売却することで多額の売却益を得ることができる」、「IPO後に株式を保有し続けることもでき、その株式は市場でいつでも好きなタイミングで売却することができる」、「IPOに成功した場合、M&Aの時よりも高い企業価値が付きやすい」と言えます。
上場企業となるため、多数の投資家が市場で自由に対象会社の株式を売買することができます。また、当然ながら、IPO後に経営者が残って経営することもでき、市場で増資するなど資金調達の幅を広げることができます。
会社が世間に広く認知されるようになることから、優秀な人材を集めやすくなります。また、上場することによって信頼も増すことから、事業承継M&Aの買い手も見つけやすくなります。
デメリット
IPOのデメリットは、「誰もが上場できるわけではなく、成功確率が低い」、「上場準備のために多額のコストが必要になる」と言ったことが考えられます。IPOはM&Aよりもさらに成功確率が低い選択肢となります。スタートアップ企業は国内に数多くありますが、IPOできる企業は、一握りの企業に限られます。IPOを目指す場合、企業の価値を引き上げることや経営に相当コミットしなければならない点は留意すべきです。単に事業承継したいためといった理由のみだと、IPOの選択肢は、かなり難しく、あまりお勧めすることはできません。
廃業
「親族外承継」「親族内承継」「M&A」「IPO」のいずれでも後継者不足を解消できない場合は、廃業せざるを得ません。たしかに廃業は回避したい選択肢ですが、業績や経営環境次第では、どうしても後継者不足を解決できないケースも考えられます。
したがって親族外承継などの方法で後継者不足の解決を目指すと同時にやむを得ず廃業する場合にも備えておくことも重要となります。
例えば、従業員の再就職先を選定しておいたり、事業用資産の売却先を見つけておいたりすることはもちろん、廃業に必要な費用を見積もり・準備することも大切になってきます。
あらかじめ廃業時の行動も明確にしておけば、やむを得ず廃業するとなった場合に従業員や家族に迷惑をかけずスムーズに事業をたたむことができます。
メリット
廃業のメリットとしては、M&Aや事業承継で起こり得るトラブルを回避でき、買い手や後任への引継ぎ・交渉そのものが不要で、オーナーの裁量で停止時期を柔軟に決めやすい点が挙げられます。
廃業手続では時価資産から負債を差し引いた残余財産を確定・回収しやすく、事業売却後に「きちんと経営されているか」を気にかけ続ける必要もありません。結果として、子どもなどの親族に個人保証や経営上のリスクを背負わせなくてよいという安心感も得られます。
デメリット
一方でデメリットとしては、中小企業庁の調査でも、継続性・成長性が見込めるにもかかわらず廃業予定の企業が約4割に上るなど、存続可能な事業まで失われるおそれがあります。
負債が残れば経営者本人や連帯保証人が返済を負う必要があり、また廃業時の評価は時価ベースとなるため将来利益が反映されず、M&Aと比べてオーナーの受取額が低くなり得ます。
さらに、従業員の雇用喪失、主要取引先の経営悪化・連鎖倒産、地域の生活インフラとしてのサービス縮小など経済・社会への悪影響が大きく、企業が蓄積してきたノウハウや技術も失われます。
黒字であっても毎年一定数が廃業を選択している現実はあるものの、継続の可能性が少しでもある場合には、M&A等の第三者承継を含めて慎重に再検討することが望まれます。
後継者不足で廃業した企業事例
- 岡野工業:世界的な微細加工技術を有しながら、後継者不在で2018年に廃業。
- 千代泉酒造所:後継者・引継ぎ先不在が続き、2018年に廃業。
- 京菓子匠 源水:約200年の老舗だが後継者不在で2018年閉店。
- 上田合金所:社長急逝・負債等により2015年廃業。
- 梅の花本舗:「元祖梅ジャム」生産終了。店主が自ら廃業を選択。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
後継者不足を解決するポイント
後継者不足の原因や対策にはそれぞれメリット・デメリットがあります。経営者としては、それらを踏まえたうえで、後継者不足を解決するためのポイントを理解しておく必要があります。以下で解説します。
早めに準備・対策を始める
後継者候補が見当たらない状況では、早めに準備・対策を始めることが最も重要です。現在の経営者が急に事業をやめざるを得ない事態で後継者がいなければ、廃業しか選択肢がなくなります。準備が遅れるほど選択肢は狭まるため、選択肢が豊富なうちに手を打つことが大切です。
早めに進められれば、親族・社内承継、M&A、IPOなどを比較検討でき、じっくりと後継者を選べます。後継者側も十分な準備期間があった方が、引継ぎ後の経営が安定しやすいといえます。
M&Aで後継者を探す場合にも、時間に余裕があるほど売り手に有利な交渉が可能です。時間がないと相場より安い価格で売却してしまうリスクが高まり、仮にM&Aが不調でも親族・社員承継へ切り替える等の二段階対応が取りにくくなります。
会社や事業の価値を高める
後継者は、引き継ぐ会社や事業の価値が低いと承継意欲を持ちにくく、借入が多く債務超過なら「無償でも引き継ぎたくない」こともあります。M&Aでも企業価値が低ければ買い手の評価が伸びず、買いたたかれるおそれがあります。納得のいく条件で承継するためにも、平時から価値向上に取り組むことが重要です。
もっとも、企業価値は一朝一夕では高まりません。売上向上やコスト削減などの積み重ねが必要で、同時にブランドや人材・顧客との関係といった無形資産を損なわない配慮も欠かせません。
ここからは、上記の「早期着手」と「価値向上」を実務に落とし込むための具体策として、①後継者育成の計画(サクセッションプラン)、②第三者承継(M&A)に備えた磨き上げ、③公的支援の活用、を順に整理します。
サクセッションプラン(後継者の選定・育成)
社内では、営業・財務・会計などの部署ローテーションで業務全体を把握させ、意思決定や交渉を任せる権限移譲によって「経営の経験値」を計画的に積ませます。
小規模でも新規事業等をリードさせて逆風下での判断力・実行力を鍛え、現経営者の継続的なフィードバックで自社に固有の経営スキルを定着させます。
社外では、ビジネススクールや各種セミナーで基礎を補強し、人脈形成を図り、必要に応じて他社勤務や関連会社・子会社への出向で俯瞰的な視野と実践力を養います。
M&Aに向けた準備(企業評価・DDを見据えた磨き上げ)
第三者承継(M&A)を視野に入れる場合、買い手はインカム・コスト・マーケットの各アプローチで企業価値を評価し、デューデリジェンス(事業・財務・法務等)でリスクを確認します。
売り手はこれを踏まえ、主力事業の収益性強化、在庫圧縮や不要資産の整理、有利子負債の適正化、内部統制の整備などを早期に着手して「買い手のメリット」を具体化して提示することが重要です。
公的支援・相談窓口の活用
これらの取り組みを財務面・実務面で後押しする制度として、事業承継・引継ぎ補助金(経営革新・専門家活用・廃業・再チャレンジ)、小規模企業共済の事業承継貸付け(低金利の資金調達)、事業承継・引継ぎ支援センター/よろず支援拠点(全国の相談窓口)などが利用できます。制度の要件・期間は年度で変動するため、最新情報の確認が不可欠です。
まとめ
これまで見てきた通り、中小企業を中心とする後継者不足は、これからの日本の社会的な課題の一つです。後継者が見つからない経営者には、親族・親族外への事業承継、M&A、IPOといった選択肢がありますが、それでも後継者が見つからない場合には廃業するしか道がなくなります。
子供などの親族が事業を引き継いでくれれば、世代交代が進みやすいと言えますが、子供の側に親の事業を継ぐ意思がなければ実現できません。
そこで、後継者不足の問題解決の有力な方法の一つがM&Aだと言えます。M&Aが今まで以上に利用されることにより、後継者不足で廃業せざるを得なかった事業をM&Aの買い手に引き継いでもらえる可能性が広がります。
一方でM&Aを行うためには、事業売却完了まで時間がかかり、誰もがM&Aで売却できるわけではない点には留意が必要です。
M&Aで売却手続を進めてみたものの、M&Aで思ったような買い手がなかなか見つからなかったり、M&A買い手との交渉がうまくいかずM&Aが破談になってしまったりというケースはM&Aでは数多く起こります。
そのため、適切なM&Aの専門家に相談しつつ、現在の経営者の意向にあったM&Aの後継者を粘り強く探していくことが必要となります。
納得のいくM&Aを実現させるためには、M&Aのための事前の綿密な準備が必要不可欠です。一朝一夕で企業価値が上がることはありませんが、日々の小さな経営改善の積み重ねで、数年後には大きな差が付くこともあります。
また、適切なM&A手数料体系のM&A専門家に相談することで、M&A事業承継の際に、M&Aを行うことで得られる自分の手取額を最大化することもできます。
このように、後継者問題はとても難しい問題ではありますが、適切に対応すれば、現在の経営者が望むような結果に結びつけることができる可能性が高まります。
ですから、経営している会社の後継者が見つからないような状況なら、適切なM&A専門家に相談することが大事な会社を存続させるためには重要だと言えるでしょう。
黒字廃業の増加、雇用・地域への影響を踏まえ、廃業のメリット・デメリットを正しく理解したうえで、親族・従業員承継やM&A等を含む最適解を早期に選択することが重要です。専門家と公的支援の活用で、実行可能性は大きく高まります。