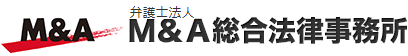家族信託は遺留分の対象となる?家族信託契約が無効になる流れとは

高齢者の親などが特定の子供に自身の財産の管理を任せることを家族信託と言います。この家族信託を行っていて、その後、委託者である親が死亡した場合、家族信託契約によって財産の移転が行われる一方、亡くなった親の財産の相続が発生します。
その際、家族信託で財産の管理をしていた特定の子供以外の相続人の遺留分をどのように扱うか?という問題が発生します。
家族信託の契約では、信託する財産の承継者を定めることができますが、委託者の親が死亡すると、場合によっては、家族信託契約での承継と委託者である親の相続人の遺留分の侵害額請求権の主張に対立が起こります。
今回は、このような場合に、家族信託の契約による承継と遺留分との関係をどのように考えればよいのかについて詳細解説をします。
家族信託とは
家族信託は、財産管理の手法の一つで、委託者の所有する財産の管理・処分を家族が受託者となって委託者に代わって行うというものです。
具体的なケースで言うと、高齢になった親が、自分で財産が適切に管理できなくなる前に、家族信託契約によって、信頼できる子供などの家族に財産の管理・処分を任せるというのがこれに当たります。
高齢の親が認知症や要介護状態などになって判断能力がなくなると、銀行口座の預金が下ろせなくなったり、自宅などの財産を適時適切に売却できなくなったりして、資産が凍結してしまうことにもなりかねません。
一方で、自らの財産を管理できない親が生活していくうえで必要な日常の経費は本来、自らの財産で賄うのが当然です。
よって、家族信託によって、委託者である高齢者の親の財産が適正な判断によって管理・処分されながら、生活が維持されることは、委託者にとって望ましい状況と言えます。
このような、適正な財産管理が必要であるというニーズに対応する手段として家族信託は非常に便利な手法です。
家族信託は、通常の所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用・処分できる権利」に分けて、後者を信頼できる家族などに与える契約です。
これを法律的に分解すると、「委託者」「受託者」「受益者」に分けることができます。「委託者」は家族信託契約で財産の管理・運用・処分を依頼する人、「受託者」はそれを依頼される人、「受益者」は「受託者」による財産の管理・運用・処分での利益を受け取る人となります。
通常、家族信託契約が開始されるとき、契約を依頼する「委託者」と利益を受け取る「受益者」は一致しています。例えば、親が自分の持つ財産を信頼できる子供に家族信託する場合、「委託者」と「受益者」は親で、「受託者」は子供になります。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、一般的に、亡くなった人からの遺言または相続によって受け取る財産ではなく、亡くなった人の死亡を原因として受け取る財産のことを言います。
典型的な「みなし相続財産」は、生命保険金と死亡退職金です。例えば、父親が子供を受取人とする生命保険に加入していた場合、父親が死亡すると子供に保険金が入ることになります。この保険金は、みなし相続財産ということになります。また、父親が死亡したことによって会社から支払われる死亡退職金も同様にみなし相続財産とされます。
みなし相続財産は厳密に言うと財産ではありませんが、生命保険の保険金や死亡退職金が発生する原因となる対象者が亡くなったことで財産となります。
このような「みなし相続財産」には、相続される財産と同様、相続税がかかります。前述のとおり、「みなし相続財産」は厳密な意味では相続財産ではありません。
しかし、被相続人の死亡によって相続人に財産が移転するという点では、相続財産と何ら変わりはありません。よって、相続財産ではなくても、被相続人の死亡によって移転する財産については、相続財産と同様に考え、「みなし相続財産」とすることで、課税の不公平をなくす意味があります。
遺留分とは
遺留分とは、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹以外の法律で定められた相続人(法定相続人)が、遺言などの内容に関係なく、最低限被相続人の財産の相続を主張できる遺産相続の取り分のことです。
被相続人の配偶者や子供などの法定相続人は、例えば、被相続人がお世話になった特定の人に対して、すべての財産を相続させると法律的に有効な遺言を残したとしても、法定相続人はそれぞれの遺留分を主張して一定の財産を取得することができます。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1)です。
よって、被相続人の法定相続人が妻と子供2人であった場合、その遺留分は、妻が法定相続分である2分の1の半分である「4分の1」、子供2人はそれぞれ4分の1の半分である「8分の1」となります。
家族信託と遺留分の関係
前述のとおり、家族信託では、通常の所有権が「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理・運用・処分できる権利」に分解されて、家族信託契約で財産の管理・運用・処分を依頼する「委託者」、それを依頼される「受託者」、財産の管理・運用・処分での利益を受け取る「受益者」に分かれています。
通常、家族信託契約が開始した時には、親などの家族信託契約の「委託者」と利益を受け取る「受益者」は一致しています。しかし、その親などが亡くなった場合、利益を受け取る「受益者」の権利である「受益権」はどのなるのか?という問題が発生します。
また、一方で、家族信託の「委託者」であり「受益者」である人が亡くなった場合、その相続人が最低限受け取る権利がある遺留分はどのように扱われるのか?という問題が発生します。
家族信託の受益権はみなし相続財産となるのか
前述のとおり、生命保険や死亡退職金のように、亡くなった被相続人の財産ではないけれども、被相続人の死亡を原因として誰かが受け取る財産のことを「みなし相続財産」と言います。では、家族信託の受益権は「みなし相続財産」なのでしょうか?
家族信託の受益権は、委託者が所有している財産を管理・運用・処分することによって発生する利益を享受する権利です。委託者かつ受益者である被相続人が亡くなった場合、その受益権は誰かに移転することになります。
家族信託契約では、委託者兼受益者である被相続人が亡くなった場合に誰に受益権が移転するかを決めることができます。
例えば、父親が委託者兼受益者、子供が受託者であった場合、父親が亡くなった場合には、母親に受益権が移転するという契約もすることができます。
この場合に、母親に移った家族信託の受益権は「みなし相続財産」となります。これは、父親にかけられていた生命保険の保険金が、父親が亡くなることによって母親に入ることと何ら変わりがないと考えられているからです。
このことは、相続税法第9条の2にも定められていて、生命保険の保険料や死亡退職金と同様、相続税の課税対象となっていることからもわかります。
家族信託が無効になる場合
家族信託は本来、親などの委託者が認知症や要介護状態などになって判断能力がなくなる前に、信頼できる家族に所有する財産の管理・運用・処分を委託して、適時適切に受益者に利益を還元してもらうことを目的に行われるものです。
適正な目的で行われる家族信託の受益権は、生命保険の保険金や死亡退職金と同様に、遺留分の侵害額請求権の侵害には当たらないとの法解釈がされていたこともありました。
通常の生命保険の保険金や死亡退職金は、受取人固有の権利であり、遺産分割協議や遺留分請求の対象とはならないという判例が確立しています。
一方で、これらのものであっても、著しく不公平で、遺留分を侵害する目的で行われるもの、については無効であるという判決が出ています。
よって、家族信託契約についても、遺留分の請求を逃れることを目的としたものについては、無効とされると考えられるようになってきています。
判例から見る家族信託と遺留分との関係性
家族信託契約と遺留分の侵害額請求権との関係についての最高裁判決は現在のところ出ていません。
よって、下級裁判所での裁判事例から、現在の裁判所が考えている家族信託契約と遺留分侵害請求権の関係性の傾向をつかむことにより、争いとなった場合の傾向を判断することになります。
家族信託契約と遺留分の侵害額請求権との関係について判断した判決としては、平成30年9月12日の東京地裁判決が知られています。
この裁判は、不動産などを有する父親Aが、長男B、次男C、次女Dに受益権を相続する家族信託契約を作成し、その後父親Aが亡くなってその契約書のとおり財産の移転が行われたが、その内容が、長男Bの遺留分を侵害したとして訴訟になった事件です。裁判の概要は次のようなものです。
父親Aはその所有する財産について家族信託契約を作成しました。当初受益者は委託者である父親Aで、受託者は次男C、父親のAが死亡した場合には、①長男Bに6分の1の受益権 ②次女Dに6分の1の受益権、③次男Cに6分の4の受益権、そして④さらにその後継受益者を次男Cの子供らとするものでした。
信託事務としては、受託者の次男Cが信託金銭を用いて信託不動産の維持管理に必要な費用を支払い、また、金銭信託を受益者の身上監護のために使用できるという定めが置かれました。
受益権の内容としては、信託不動産の売買代金や賃料等、信託不動産より発生する経済的利益を受け取ることができるという内容が定められました。
その後、父親Aが死亡し、信託不動産は家族信託契約の受託者である次男Cに移転して所有権移転登記などが行われました。
しかし、そもそもこの信託不動産には、受益権の利益を生み出す不動産のほかに、収益性も換価処分性もない不動産も含まれており、受益権の対象となる経済的利益を生まないこれらの不動産もそのまま信託契約によって次男Cに移転するということについて、長男Bは不服として訴訟を起こしました。
長男Bは、受益権の対象となる賃料や売買代金の利益を生み出す不動産以外に収益性も換価処分性もない不動産をわざわざ信託不動産に含めた父親Aと次男Cとの家族信託契約について、長男Bの遺留分の侵害目的であるから無効であると主張しました。
東京地方裁判所は、長男Bの主張を認め、収益性も換価処分性もない不動産の部分については、「遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるというべきである」と判断しました。
この裁判は、その後、控訴審で和解となったため、これ以降の裁判所の判断はありませんが、家族信託契約であっても、公序良俗に反する場合は無効となるという指針を示したものと考えられています。
遺留分対策について
ここまで見てきたとおり、現状においては、家族信託契約の受益権は、相続税法では「みなし相続財産」として扱われているものの、公序良俗に反すると考えられた場合、遺留分の侵害請求権には対抗できないこともあります。
一方で、家族信託契約の「委任者」かつ「受益者」である被相続人や「受託者」の家族からすると、被相続人が死亡した場合には、特定の相続人以外の相続人の遺留分をできるだけ小さくしたいという想いがある場合も想定されます。
このような場合に、家族信託契約以外にも、被相続人が存命中に可能な限り遺留分対策をしておくことが望ましいと考えられます。そこで、ここからは遺留分対策について説明することにします。
遺留分放棄
遺留分放棄は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている遺留分の権利を、法定相続人自ら手放すことを言います。
法定相続人が遺留分を放棄すれば、その人は遺留分侵害請求ができなくなりますので、家族信託契約で受益権が被相続人から特定の家族に移転しても、遺留分放棄した法定相続人から遺留分を請求されることはありません。
しかし、遺留分放棄は、法定相続人自らの意思で行われる必要があるので、被相続人が家族信託契約で自らの財産の受益権を特定の家族に譲り渡したいと思っても、本人が遺留分放棄の意思がなければ、遺留分放棄を成立させることはできません。
また、被相続人が生存中に法定相続人に遺留分放棄をしてもらうためには、家庭裁判所の許可が必要です。よって、家族信託契約の受益権を思うように引き継いでもらうためには、法定相続人を説得したりすることで、自らの意思で遺留分放棄を促すようにするしかありません。
相続欠格・相続廃除
被相続人の法定相続人の中に、相続欠格や相続廃除の対象となる人がいる場合には、その手続きを行うことで遺留分対策になります。
相続欠格は、法定相続人が民法891条に定められた5つの欠格事由に該当する場合に、遺留分も含めた相続権を剥奪することを言います。
5つの欠格事由は、
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
であり、相続秩序を侵害する非行をしたとして、その相続権が剥奪されます。
次に、相続廃除は、被相続人が自らの意思で、遺留分がある特定の推定相続人に対して、相続権の剥奪をすることができます。
相続廃除ができる法律上定められている廃除事由は民法892条に定められていて、「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」の3つです。
「虐待」は、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること、「重大な侮辱」は被相続人の名誉や感情を著しく害すること、「著しい非行」は、虐待・重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行をいいます。
例えば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明等です。
これらに該当する遺留分がある推定相続人に対して、被相続人は家庭裁判所で認められれば、相続人廃除を行うことができます。
遺言書への記載
遺言書に被相続人の意思として、家族信託契約をしている自らの財産を契約で定めた家族に移転させたいことを書き残すことも考えられます。
しかし、遺言書に記載しても、法的には、被相続人の死後に遺留分放棄を法定相続人にお願いするという意味にしかならず、結局、「法定相続人が自らの意思で遺留分放棄をしてもらうことを希望している」と被相続人が表明することにしかなりません。
よって、実効的な遺留分対策としては、他の方法を取るということが現実的と言えます。
養子縁組
例えば、家族信託契約をしている特定の家族の子供と養子縁組をすることで、被相続人の法定相続人の直系の親族が増えることになり、例えば、子供同士のそれぞれの法定相続人の遺留分割合を減らすことができます。
しかし、配偶者の遺留分割合を減らすことはできませんし、それぞれの法定相続人(例えば被相続人の子)の遺留分の割合を減らすことはできても、完全になくすことはできないため、遺留分のある法定相続人が主張した場合、何らかの形で遺留分相当の財産を渡す必要が出て来ます。
生前贈与
生前贈与を行うということも遺留分対策としては考えられます。相続人への生前贈与は10年間、相続人以外への生前贈与は1年間が経過すると、遺留分を算定する基礎財産から除外されることが法律で定まっています。
これを利用して、被相続人から家族信託契約を行っている家族などに計画的に生前贈与を行い、それ以外の相続人の遺留分の算定基礎財産を減らしていくという手法も取ることができます。
また、さらに踏み込んで、被相続人から生前贈与を受けた相続人であっても、相続放棄をした場合には、もともと相続人ではない人として扱われることを利用して、財産を与えたい相続人に、被相続人の死亡の1年前までに財産を生前贈与して、被相続人が死亡してからその相続人に相続放棄をしてもらうという方法を取ることも考えられます。
これらの方法を取れば、被相続人が財産を引き継いでもらいたい特定の相続人などに財産の多くを引き継ぐこともできます。
しかし、通常の生前贈与であると被相続人の死亡の相当前から計画的に贈与を続けなければならず、一方で生前贈与と相続人放棄の方法を取った場合には、他の相続人の遺留分を減らす目的があまりに露骨な場合には、公序良俗違反で無効を主張される可能性があります。
また、生前贈与には、当然、贈与税が課税されるということも注意が必要です。
生命保険
生命保険による死亡保険金の支払額は、基本的には、遺留分を算定する基礎財産には含まれません。これは、生命保険が保険会社から支払われる受取人固有の財産だと考えられているからです。
平成16年10月29日の最高裁判決でも、生命保険契約によって発生する「死亡保険金が遺留分の計算に含まれないことが原則である」とされています。
しかし、同じ最高裁の判決で「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となると解する」とされています。
つまり、被相続人が付保していた生命保険による特定の人に対する死亡保険金は、遺留分を算定する基礎財産には含まれないが、その額が他の相続人と比較してあまりにも不公平に多額である場合には遺留分を算定する基礎額に持ち戻して計算することになるということです。
生命保険の死亡保険金の額が他の相続人が相続する被相続人の遺産と比較して不公平かどうかの判定は、それぞれの事案の具体的な事情によって判断されます。
よって、単に生命保険の死亡保険金の額と他の相続人が相続する相続財産の額による比較だけではなく、例えば、生命保険の死亡保険金を受け取った人の被相続人に対する寄与分なども考慮して、不公平であるかどうかが決められます。
家族信託のまとめ
今回は、被相続人が家族信託をしていた場合の家族信託契約と各相続人の遺留分との関係について解説しました。
家族信託の受益権と遺留分の関係については、現在のところ、最高裁判所での判断は出ていないものの、下級裁判所では判決が出ており、遺留分を侵害することを目的とした家族信託契約は無効であるとの判断になっています。
一方で、相続人の遺留分請求があると、家族信託契約によって被相続人が自分の所有している財産を相続人の中の特定の者に引き継いでいってほしいという想いに反することになる可能性もあります。
これらのバランスをどのように取るのかという判断基準が明確になって行くためには、今後の同様の事例への地方裁判所や高等裁判所の判決の蓄積や最高裁の判決が出るのを待つ必要があると思います。