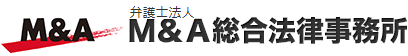事業承継M&Aのメリット・デメリットを売り手と買い手の視点で解説
お困りではありませんか?

経営者の高齢化や後継者不足が深刻化するなか、近年「事業承継M&A」が注目されています。
会社を第三者に譲渡することで、会社の存続や従業員の雇用を守ることができる一方で「本当にM&Aを選んでよいのか」「どんなメリット・デメリットがあるのか」と悩む経営者も多いでしょう。
本記事では、事業承継M&Aのメリット・デメリットを売り手と買い手の両視点からわかりやすく解説します。事業承継M&Aのために知っておきたいポイントも紹介するので、事業承継M&Aを成功させたい方はぜひ参考にしてください。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
事業承継M&Aとは?
事業承継M&Aとは、後継者がいない企業が自社の事業や株式を、第三者である別の企業や個人に譲渡(売却)して引き継ぐ手法を指します。
近年では、経営者の高齢化が進み、子どもや親族に事業を継がせることが難しい中小企業が増えています。そのような背景から親族以外の第三者に承継する「第三者承継」としてM&Aを活用するケースが急増しています。
M&Aと聞くと「会社を売る」「買収される」というイメージを持つ方も多いですが、事業承継M&Aは単なる売買ではありません。会社を存続させ、従業員の雇用や取引関係を守りながら、次の経営者に事業を引き継ぐ発展的な承継としての側面があります。
M&Aによる事業承継のスキーム(3つ)
M&Aによる事業承継は主に3つのスキームがあります。
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 会社分割
事業承継M&Aは単なる経営者交代ではなく、会社を次世代へとつなぐ重要な経営戦略の一つです。後継者問題を抱える経営者にとっては、会社の存続と従業員の将来を守るための有力な選択肢となっています。
それぞれ詳しく解説します。
株式譲渡
株式譲渡は、一般的な事業承継M&Aの手法です。
売り手が保有する株式を買い手に譲渡することで、会社の経営権を移転します。会社の法人格はそのまま維持されるため、取引契約や従業員の雇用・許認可なども基本的に引き継がれます。
株式譲渡の手続きは比較的シンプルで、スムーズに承継を進められます。しかし、会社が抱える債務やリスクも引き継がれるため、事前のデューデリジェンス(企業調査)が重要になります。
事業譲渡
事業譲渡とは、特定の事業や資産・契約などを選択的に譲渡する方法です。
買い手は必要な事業だけを取得できるため、リスクを最小限に抑えられます。一方で、譲渡対象ごとに契約の再締結が必要になるため、手続きが複雑になりやすい点がデメリットです。
また、従業員の雇用契約や取引先との関係も個別対応となるため、慎重な調整が求められます。とはいえ、事業の一部のみを切り離したい場合には、非常に有効なスキームです。
会社分割
会社分割は、会社の一部事業を新会社や他社に分けて承継させる方法です。
主に「吸収分割」と「新設分割」の2種類があり、どちらも法的手続きを通じて移転できます。 この方法は、特定事業を分離して再編したい場合や、グループ内での事業整理を進めたい場合に有効です。
株式譲渡や事業譲渡に比べて手続きは複雑ですが、税務上のメリットが得られるケースもあります。 経営再編と事業承継を同時に進めたい企業にとって、柔軟性の高い選択肢といえるでしょう。
事業承継M&Aがなぜ必要か?
日本では、経営者の高齢化が年々進み、中小企業の約3分の2が60歳以上の経営者と言われています。
しかし、後継者が見つからず、黒字経営であっても廃業を選ぶケースが増えています。中小企業庁の調査では、後継者不在を理由に年間4万社以上が廃業しており、地域経済への影響も深刻です。
このような状況のなか、事業承継M&Aは会社を存続させるための現実的な解決策として注目されています。経営者が引退する際に、親族や社員に後を継がせるのではなく、外部の企業や投資家へ事業を譲渡することで、事業そのものを次世代につなぐことができます。
M&Aによる承継を選べば、従業員の雇用や取引先との関係を維持したまま、経営資源を有効に活用できます。さらに、買い手企業にとっても新規事業への参入や地域展開のチャンスとなり、双方にメリットが生まれます。
単なる会社売却ではなく、「自社が築いてきた価値を未来に残すための選択肢」として、事業承継M&Aの必要性は今後さらに高まっていくでしょう。
事業承継の3つの方法とM&Aの立ち位置
事業承継方法には大きく3つの方法あります。
- 親族内承継
- 従業員承継
- M&A承継
それぞれの承継方法を表にまとめました。
| 承継方法 | 主な後継者 | メリット | デメリット |
| 親族内承継 | 子供や親族 | ・経営理念を引き継ぎやすい ・社内の理解を得やすい |
・後継者の経営能力に左右される ・相続・贈与税の負担が大きい |
| 従業員承継 | 役員や幹部 | ・経営の継続性が高い ・従業員の安心感がある |
・資金調達が難しい ・経営責任を負う必要がある |
| M&A承継 (第三者承継) |
他社や投資家など | ・後継者不在でも会社を存続できる ・創業者利益を得られる |
・買い手と条件交渉が必要になる ・会社の文化の違いで摩擦が生じることもある |
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、会社の状況や経営者の意向によって最適な選択肢が異なります。
1990年代までは親族内承継が主流の承継方法でした。若年後継者の人数不足や価値観の多様化から2000年代以降は親族外承継やM&A承継に承継方法が大きく移り変わってきています。
少子高齢化や後継者不足が進む今、M&Aは事業承継の最後の選択肢ではなく、「戦略的な選択肢」として位置づけられています。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
事業承継M&Aのメリット(売り手側)
事業承継M&Aのメリットは主に以下のとおりです。
- 後継者問題と会社の存続を解決できる
- 創業者利益を獲得できる
- 経営者の個人保証・担保から解放される
それぞれ詳しく解説します。
後継者問題と会社の存続を解決できる
中小企業の多くが抱える最大の課題は「後継者不足」です。親族や社員の中に適任者が見つからない場合、最悪のケースでは黒字にもかかわらず廃業に追い込まれることがあります。
しかし、M&Aによる事業承継なら、外部の企業や投資家に事業を引き継ぐことで、会社を存続させることが可能です。既存の従業員の雇用を守りながら、取引先や顧客との関係も継続できるため、経営者にとって「自分が築いた会社を残せる」という大きな安心感があります。
創業者利益を獲得できる
事業承継M&Aを活用することで、経営者は自社株式を売却し、対価としてまとまった金額を得られます。これが「創業者利益(キャピタルゲイン)」です。
長年の経営努力が資産として評価されるため、老後の生活資金や新たな事業への投資資金として活用できます。また、廃業による清算では得られない価値を実現できる点も、M&Aの大きな魅力です。
単なる引退ではなく、「会社を次のステージへ託しながら利益も得る」という理想的な出口戦略となるでしょう。
経営者の個人保証・担保から解放される
中小企業経営では、金融機関からの借入時に経営者個人が保証人となるケースが一般的です。そのため、事業に問題が起これば個人資産にも影響が及ぶリスクがあります。
しかし、事業承継M&Aによって会社を譲渡すれば、基本的に新しいオーナーが債務や保証を引き継ぐことになります。
これにより、経営者は個人保証や担保から解放され、精神的にも経済的にも負担が軽減されます。リタイア後の人生設計を安心して描ける点も、M&Aを選ぶ大きな理由の一つです。
事業承継M&Aのデメリット(売り手側)
事業承継M&Aのデメリットは主に以下のとおりです。
- 希望通りの条件で売却できないリスク
- 従業員や取引先の反発や人材流出のリスク
それぞれ詳しく解説します。
希望通りの条件で売却できないリスク
事業承継M&Aを進める際、売り手が希望する価格や条件で必ずしも契約が成立するとは限りません。
買い手は自社の利益やリスクを踏まえて査定を行うため、経営者が想定していた金額よりも低くなるケースもあります。また、会社の業績や将来性・業界動向などによって評価が変動するため、タイミングの見極めも重要です。
交渉を有利に進めるためには、複数の候補企業を比較し、専門家のサポートを受けながら妥当な条件を見極める必要があります。
従業員や取引先の反発や人材流出のリスク
事業承継M&Aによって経営者が交代すると、従業員や取引先が不安を感じて反発や人材流出のリスクがあります。
特に、経営者への信頼が業務を支えていた場合、社長が変わるなら辞めるといった人材流出のリスクも考えられます。さらに、取引先との契約条件が見直されたり、取引量が減少したりするケースもあります。
これらのリスクを防ぐためには、情報開示のタイミングや説明の仕方が非常に重要です。M&Aの目的や今後の方針を丁寧に伝え、関係者の理解を得ながら進めることが成功のカギになります。
事業承継M&Aのメリット(買い手側)
事業承継M&Aのメリットは主に以下のとおりです。
- 新規事業へスピーディに参入できる
- 優秀な人材や技術を一気に獲得できる
- シナジー効果による市場シェアの拡大ができる
それぞれ詳しく解説します。
新規事業へスピーディに参入できる
買い手側にとって事業承継M&Aは、時間をかけずに新しい市場へ参入できる点が魅力の一つです。
ゼロから事業を立ち上げる場合、商品開発・人材採用・顧客獲得など多くのステップが必要ですが、事業承継M&Aなら既に実績のある会社を引き継ぐことで、すぐに事業展開できます。
特に成長産業や地域密着型の業種では、スピード感のある展開が競争優位につながります。自社の経営資源を効率的に活用しながら、新規分野への進出を実現できる点は大きなメリットです。
優秀な人材や技術を一気に獲得できる
事業承継M&Aでは、買収先の会社に在籍する人材やノウハウ、技術力をそのまま引き継ぐことができます。
特に、専門技術を持つ職人や開発チーム、地域で信頼を築いた営業スタッフなどは、短期間で育成するのが難しい貴重な資産です。
このような人材や技術を獲得することで、自社の弱点を補いながら組織力を強化できます。また、他社にはない製品開発力やサービス品質を取り込むことで、競争力の向上にも直結します。
シナジー効果による市場シェアの拡大ができる
事業承継M&Aによって、既存事業とのシナジー効果を生み出せる点も買い手にとって大きなメリットです。
たとえば、顧客基盤や販売ルートを共有することで、売上拡大やコスト削減を実現できる可能性があります。また、技術・人材・ブランドを組み合わせることで、新しい価値を生み出すことも可能です。
その結果、自社単独では到達できなかった市場規模やシェア拡大を、M&Aによって短期間で実現できる可能性があります。
事業承継M&Aのデメリット(買い手側)
事業承継M&Aのメリットは主に以下のとおりです。
- 期待したシナジー効果が得られない
- 簿外債務などを引き継ぐリスクがある
それぞれ詳しく解説します。
期待したシナジー効果が得られない
買い手側はシナジー効果に期待して事業承継M&Aを実行します。
しかし、実際に統合してみると、企業文化や経営方針の違いにより思うような成果が出ないケースも少なくありません。
特に、組織風土や人材マネジメントのスタイルが異なる場合、現場の混乱やモチベーションの低下を招くことがあります。その結果、売上の伸び悩みや人材流出につながり、当初想定していたシナジー効果を得られない可能性もあります。
このような失敗を防ぐためには、M&Aの前段階で統合計画(PMI)をしっかりと立て、買収後の運営体制まで見据えた戦略的な準備が不可欠です。
簿外債務などを引き継ぐリスクがある
事業承継M&Aでは、対象企業のすべての資産・負債を引き継ぐため、帳簿に記載されていない簿外債務や将来的なトラブルのリスクを抱える可能性があります。
たとえば、未払いの税金や退職金・環境問題・訴訟リスクなど、デューデリジェンスでは見抜けない項目が後から発覚するケースもあります。
このような問題が発生すると、予想外のコスト負担や経営悪化につながりかねません。 そのため、買い手側は専門家と連携し、法務・財務・税務面を徹底的に精査しましょう。
また、契約書に表明保証条項を設けることで、リスク発生時の責任範囲を明確にしておくと安心です。
⇒事業承継対策(紛争対策・相続税対策・株価対策・後継者対策)なら!
事業承継M&Aを成功させるためのポイント
事業承継M&Aを成功させるためのポイントは主に以下のとおりです。
- 自社の価値を正確に把握する
- 信頼できるM&A専門家に依頼する
- 情報管理の体制を徹底する
それぞれ詳しく解説します。
自社の価値を正確に把握する
事業承継M&Aを成功させるには、まず自社の「企業価値」を正確に把握すること重要です。
経営者が思う理想の価格と、買い手が評価する金額には誤差が生じるため、根拠のない価格設定は交渉を難航させます。
財務データや収益構造だけでなく、顧客基盤・技術力・ブランド価値などの無形資産も含めて総合的に分析することが重要です。自社の強みを数値化し、客観的に評価することで、買い手に納得してもらえる適正な条件で交渉を進められます。
信頼できるM&A専門家に依頼する
M&Aは法律・税務・財務など幅広い専門知識を要する複雑な取引です。経営者だけで全てを対応するのは難しいため、経験豊富なM&A仲介会社やアドバイザーへ依頼しましょう。
M&A専門家は、相手企業の選定から条件交渉・契約書作成・クロージングまでを一貫してサポートしてくれます。また、第三者の立場から公正にアドバイスしてもらえるため、売却価格や条件面で不利になりにくい点もメリットです。
信頼できる専門家を早い段階で選定し、パートナーとして進めることが重要です。
情報管理の体制を徹底する
M&A交渉の過程では、従業員や取引先に情報が漏れると、社内の混乱や信用低下を招くリスクがあります。そのため、情報管理の徹底は成功に欠かせないポイントです。
具体的には、関係者を最小限にして守秘義務契約(NDA)を締結しましょう。そのうえで情報共有を行うのが基本です。また、社内での噂や外部への漏えいを防ぐためのルールづくりも必要です。
情報を適切にコントロールすることで、信頼関係を維持しながらスムーズにM&Aを進められます。
まとめ
事業承継M&Aは、後継者不在の問題を解決しながら、会社を次の世代へつなぐ有効な手段です。
売り手側にとっては、会社の存続や創業者利益の獲得などのメリットがあります。買い手側は、新規事業への参入や優秀な人材・技術の確保などの成長のチャンスを得られます。
一方で、条件交渉の難航や文化の違いによる統合リスクなど、デメリットも存在します。
事業承継M&Aを成功させるためには、自社の正確な価値の把握や信頼できる専門家のサポート・情報管理の徹底が重要なポイントです。
事業承継M&Aで失敗しないためにも、メリットやデメリットを理解した上で、準備を進めて行きましょう。
お困りではありませんか?