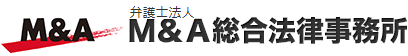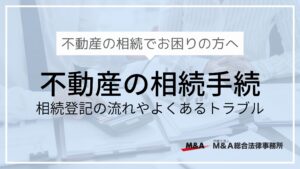株式の相続手続方法を弁護士が解説|上場株式・非上場株式の相続時の違いとは?
お困りではありませんか?
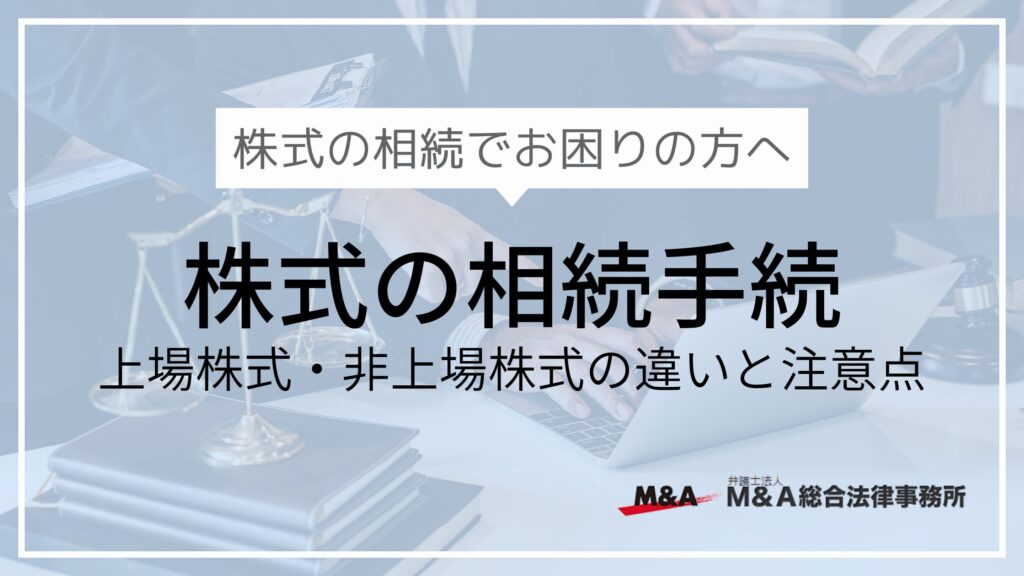
相続財産に株式が含まれる場合、預貯金や不動産と比べて手続が複雑になることがあります。
株式は上場株式と非上場株式で名義書換の方法や評価手順が異なります。とりわけ非上場株式では、会社法上の株主名簿の名義書換請求(会社法133条)や、譲渡(売買等)のみ承認が必要となる譲渡制限の有無を確認します。相続等の一般承継による取得は承認不要である一方、承認拒否時の買取義務(会社法140条)や売買価格決定の申立て(地方裁判所、会社法144条)が問題となる場面があります。
株式は財産的価値に加えて議決権等の社内的権利が伴います。このため、評価方法の選択や議決権配分をめぐり相続人間の調整が必要となることがあります。相続税の申告期限(原則10か月)までに評価資料を整備し、適法な手順で名義書換・遺産分割を進めることが重要です。
本記事では、上場株式・非上場株式の相続における手続の流れ、評価方法、留意点を整理し、弁護士に依頼することの実務上の利点と、紛争予防の観点から押さえるべき事項を解説します。
株式の相続手続の基本的な流れ
株式の相続手続きは、一般的な遺産と同様に「相続開始」から始まりますが、株式特有の調査や名義書換の工程が多く含まれます。ここでは、上場株式・非上場株式のいずれにも共通する基本的な流れを解説します。
| ステップ | やること | 主な窓口 | 期限・注意 |
|---|---|---|---|
| ① | 遺言書の有無確認・相続人確定 | 家庭裁判所/市区町村・法務局 | 公正証書・法務局保管の自筆は検認不要。 |
| ② | 相続財産に株式があるか確認 | 証券会社・株主名簿管理人/発行会社 | 上場=証券口座・特別口座、非上場=株主名簿・登記で確認。 |
| ③ | 遺産分割協議(現物/換価/代償) | 相続人間(必要に応じ専門家) | 評価基準時と権利帰属時点を明示。非上場は議決権配分に配慮。 |
| ④ | まとまらない場合の申立て | 家庭裁判所 | 調停→審判。審判に不服は告知日から2週間以内に即時抗告。 |
| ⑤ | 名義変更 | (上場)証券会社・信託銀行 (非上場)発行会社 |
相続(一般承継)は承認不要。譲渡(売買等)との混同注意。 |
| ⑥ | 相続税の申告・納付 | 税務署/税理士 | 期限:相続開始を知った翌日から10か月。未分割でも期限内申告を優先。 |
※具体的な書式・必要書類は、提出先(証券会社・株主名簿管理人・発行会社等)の指示に従って準備してください。
① 遺言書の有無を確認し、相続人を確定する
まず遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言(法務局未保管)および秘密証書遺言が存在する場合は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。検認は遺言書の存在・形式を確認し、改ざん防止のために行う手続です。これに対し、公正証書遺言または自筆証書遺言保管制度で法務局に保管された自筆証書遺言は検認不要です。
遺言書がない場合や、遺言の効力が相続人の範囲を確定しない場合は、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍一式を収集し、相続人を確定します。相続人の確定は、その後の遺産分割協議や株主名簿の名義書換等の前提となるため、早期に完了させます。
② 相続財産の中に株式が含まれているかを確認する
次に、相続財産に株式が含まれるかを確認します。上場株式は、被相続人名義の証券会社口座の残高照会に加え、特別口座(株主名簿管理人が管理)の有無を確認します。複数の証券会社を利用している可能性があるため、各社への一括照会と特別口座の株主名簿管理人への照会を並行します。
非上場株式は、株主名簿記載事項証明書、会社への照会、登記事項証明書(発行済株式総数・譲渡制限の有無)で確認します。株券電子化および株券不発行が原則であるため、株券の現物の有無に依存せず、名簿記載と会社管理情報を基準に把握します。
③ 遺産分割協議を行う
相続人が確定し、株式の存在が確認できたら、遺産分割協議を行います。株式は現金のように単純に分けられないため、分割方法・評価基準時・権利帰属時点をあらかじめ整理します。
主な方法は次の3つです。
- 現物分割:株式をそのままの形で分ける方法。銘柄・銘柄コード・株数・口座種別(特別口座の有無を含む)を協議書で特定します。
- 換価分割:株式を売却し、得た代金を分ける方法。売却主体・手続・手数料負担・税負担の扱いを明示します。
- 代償分割:一人の相続人が株式を取得し、他の相続人に金銭で補償する方法。代償金額・支払期日・支払方法を記載します。
特に非上場株式では、会社の経営権や議決権の割合に影響が及ぶため、単純な持ち分計算にとどめず、評価の基準時(例:課税時期の終値や月平均の最も低い価額)や配当・議決権の帰属時点(基準日・効力発生日)を協議書に明示します。経営方針や将来の事業承継も踏まえて調整します。
④ 遺産分割協議がまとまらない場合の対応
株式の評価や議決権配分で協議が整わない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。調停では調停委員が当事者の主張・資料を整理し、合意に至れば内容は調停調書に記載され、確定判決と同一の効力を生じます。調停不成立のときは審判に移行し、裁判所が分割方法を定めます。審判に対する不服申立ては、審判告知を受けた日から2週間以内の即時抗告で行い、抗告審は高等裁判所が審理します。株式評価に争いがあるときは、評価資料(株価証明、財務資料、相続税評価書等)を整備し、必要に応じて鑑定意見を提出します。
会社法上の価格決定等の別手続が問題となる場合は、本件遺産分割手続とは切り分けて進めます。
⑤ 名義変更手続きを行う
遺産分割協議で株式の帰属が決まったら、名義書換を行います。上場株式の場合、証券会社や信託銀行を通じて名義書換の手続きを行います。必要書類としては、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などがあります。
非上場株式の場合は、発行会社に対して株主名簿の名義書換請求(会社法133条)を行います。相続等の一般承継による取得は承認不要であり、相続を証する書面等(会社法施行規則22条)を添付して手続を進めます。取締役会等の承認が対象となるのは「譲渡(売買等)」の場合であり、相続に承認は求められません。承認が必要な類型の手続と混同しないよう、提出先と必要書類を事前に確認します。
名義書換に共通して必要となる主な書類
株式の名義書換を行う際には、相続関係を客観的資料で立証する必要があります。手続を円滑に進めるため、上場株式・非上場株式共通で求められる書類の例を以下に整理します。
- 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本(出生から死亡までを連続取得)または法定相続情報一覧図の写し
- 相続人の戸籍謄本(一覧図を用いる場合は省略可の運用あり)
- 遺産分割協議書または遺言書(公正証書遺言は検認不要)
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図(法定相続情報一覧図を提出する場合は代替可)
- 相続届(証券会社・信託銀行・発行会社の所定様式)
- 株式残高証明書または株主名簿記載事項証明書(対象株式の確認用)
上場株式では、証券会社が指定する相続届出書や特別口座の相続手続依頼書など、各社の独自書式が必要です。非上場株式では、発行会社が定める株主名簿書換請求書等の提出が必要です。書式・提出先・必要書類の細目は、発行会社または株主名簿管理人の案内に従います。
法定相続情報一覧図の写しは、法務局で無料交付(複数部可)されるため、戸籍一式の代替資料として有効です。各機関の運用により原本提示や追加書類が求められる場合があるため、提出先の指示に合わせて準備します。
⑥ 相続税の申告と納付
株式を相続した場合、その価値に応じて相続税が課されます。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。上場株式の評価は課税時期(死亡日)の終値が基本で、当月・前月・前々月の月平均のうち最も低い価額を上回る場合はその最も低い価額に置換します。非上場株式の場合は、会社の資産内容や収益、配当などを基準に算定されるため、評価には専門的な知識が必要です。
評価の誤りや申告漏れがあると、後日修正申告や追徴課税の対象となるおそれがあります。弁護士や税理士と連携して正確に進めることが望ましいです。
相続税の基礎控除と未分割申告のポイント
相続税の課税価格は、遺産総額から債務・葬式費用等を控除したうえで基礎控除額を差し引いて判定します。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3人のときは4,800万円となります。課税価格が基礎控除額以下であれば申告義務は生じません。
申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限までに遺産分割が成立しない場合でも、未分割のまま期限内申告を行います。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など一部の特例は原則として適用できません。後日に分割が成立したときは、所定の手続により更正の請求または修正申告を行い、該当特例を適用します。
期限後申告や無申告は加算税・延滞税の問題を生じるため、分割の成否にかかわらず期限内申告を優先します。分割協議の進捗と並行して、評価資料、戸籍関係、法定相続情報一覧図、各特例の適用可否に関する根拠資料を事前に整備します。
弁護士に依頼するメリット
株式を含む相続では、法律・税務・経営の要素が複雑に絡み合うため、弁護士に依頼することで得られるメリットは大きいです。特に、非上場株式を相続する場合には、手続の煩雑さだけでなく、経営権や議決権の調整など、専門的な法的判断が必要になります。ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを4つの観点から解説します。
① 相続人間のトラブルを防止できる
株式は分割が難しく、評価額も変動するため、相続人の間で意見が対立しやすい財産です。弁護士が介入することで、各相続人の権利関係を整理し、法的根拠に基づいた分割案を提示することができます。特に、非上場株式を含む相続では、「誰が株を持つのか」「どのような割合で持つのか」が会社経営に直結するため、慎重な判断が求められます。
また、弁護士が第三者として関与することで、感情的な衝突を避け、冷静で公平な協議を進めることが可能になります。相続人全員の合意形成をスムーズに行うためにも、早期の相談が効果的です。
② 非上場株の評価・分割に専門的な助言を得られる
非上場株式の評価は、税法や会計の知識に加え、事業の実態や経営状況の理解が欠かせません。弁護士に依頼すれば、税理士や公認会計士と連携しながら、適切な評価方法を選択できます。たとえば、「純資産法」か「類似業種比準法」かの判断や、会社の支配権を踏まえた分割方針など、専門家の意見を踏まえた総合的な提案が可能です。
さらに、株式の分割方法(現物分割・換価分割・代償分割)を選ぶ際にも、法的リスクを事前に確認できます。評価の妥当性に関する証拠を残すことで、後の紛争を防止する効果もあります。
③ 会社承認・議決権調整などを法的に処理できる
非上場会社の譲渡制限株式では、譲渡(売買等)に会社の承認が必要となる一方、相続等の一般承継による取得は承認不要です。相続で取得した株式は、株主名簿の名義書換請求に必要資料を添付して進めます。会社が承認しない旨を決定し、買取りの条件が整わない場合は、会社または指定買取人による買取義務(会社法140条)、協議不調時の売買価格決定の申立て(地方裁判所、会社法144条)といった手続の選択肢を検討します。
相続人が複数となる場合には、議決権割合の整理、議決権行使に関する取決め(株主間契約等)、取締役選任・定款整備を並行し、会社運営の安定を図ります。弁護士は、承認要否の判定、必要書式の整備、会社・相続人間の調整、価格決定申立ての対応までを一体的に支援します。
④ 手続の負担を軽減し、適正な分割を実現できる
株式の相続には、戸籍・協議書・承認書など多くの書類作成が必要です。弁護士に依頼することで、これらの手続きを一括でサポートしてもらえるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。特に、株主名簿の名義書換や相続税の申告に関しては、税理士・会計士との連携も必要となるため、弁護士が窓口として全体を統括することが有効です。
さらに、弁護士が関与することで、遺産分割協議書の法的有効性が担保され、後のトラブル防止にもつながります。相続を「円滑に」「正確に」進めるためには、専門家の支援が不可欠です。
【ポイント】
- 弁護士は相続人間の調整役として、感情的な対立を防ぎます。
- 非上場株式の評価・分割では、法務・税務の専門知識を総合的に活用できます。
- 譲渡制限株式における承認や議決権調整など、法的手続きを確実に実行できます。
- 書類作成や金融機関・会社との調整まで、手続の全体を一括サポートできます。
上場株式を相続する場合の手続と評価方法
上場株式を相続する場合、証券会社や信託銀行を通じて比較的明確な手続きを行うことができます。名義書換の流れや評価方法は法令や金融機関のルールに基づいており、非上場株式に比べると標準化されています。ただし、配当金や相続税の評価額など、注意すべき実務上のポイントも多くあります。
① 証券会社・信託銀行での名義変更手続
上場株式は、被相続人が証券会社の取引口座に保有している場合と、株式発行会社が信託銀行等に開設している特別口座に記録されている場合があります。どちらに保有されているかで、手続の窓口や必要書類が異なります。
【1.証券会社の取引口座に保有されている場合】
相続が発生したら、まず被相続人が取引していた証券会社に連絡します。証券会社は「相続専用窓口」を設けており、必要書類と手続書式を案内してくれます。
主な提出書類は次のとおりです。
- 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書または遺言書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 相続届(証券会社所定様式)
手続後、各相続人が株式を引き継ぐ場合は、相続人自身の証券口座の開設が必要です。新規口座を開設せずに株式を売却することはできないため、あらかじめ開設手続きを並行して進めます。
【2.特別口座(信託銀行管理)に保有されている場合】
特別口座は、株主名簿管理人(多くは信託銀行)が管理する振替制度上の管理口座であり、取引口座ではありません。被相続人が株券電子化(2009年)以前から保有していた上場株式などが記録されていることがあります。相続手続は株主名簿管理人あての相続届出から開始し、各機関所定の書式・証明書類を提出します。
主な提出書類の例(実務上は各機関の指示に従います)。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書(公正証書遺言は検認不要)
- 相続届(株主名簿管理人所定様式)
- 株式残高証明書や特別口座の記録が分かる書面(保有している場合)
売却は、証券会社の取引口座に移管した後に可能です。特別口座からの名義書換・移管は、株主名簿管理人の案内に従って進めます。処理期間や必要書類は発行会社・株主名簿管理人・証券会社の運用および提出書類の完備状況により異なります。
【3.手続時の留意点】
- 相続発生日が休日の場合は、最も近い営業日の終値を基準に評価します。
- 名義書換・移管の処理期間は、発行会社・株主名簿管理人・証券会社の運用や提出書類の完備状況により異なります。各機関の案内に従い、必要書類の事前確認と不備解消を徹底します。
- 手続進行中は名義人基準で配当金が管理されるため、相続人が受領するには未払配当の請求手続が必要となる場合があります。定款の除斥期間(例:払渡開始日から3年)の定めに留意します。
② 上場株式の相続税評価方法
上場株式の相続税評価は、課税時期(被相続人の死亡日)の最終価格(終値)を基本とします。もっとも、その終値が「課税時期の属する月」「前月」「前々月」の各月平均額のうち最も低い価額を上回るときは、その最も低い価額によって評価します(月平均は各月の全取引日の終値の平均とします)。評価は銘柄ごとに行い、合算して課税価格を算定します。
【評価の具体例(置換例)】
A社株式1,000株を相続した事例を想定します。
- 課税時期(2025年2月10日)の終値:1株=2,000円
- 2025年2月の月平均終値:1株=2,020円
- 2025年1月の月平均終値:1株=1,980円
- 2024年12月の月平均終値:1株=1,970円
上記3か月の月平均のうち最も低い価額は1,970円です。課税時期の終値2,000円はこれを上回るため、1,970円で評価します。
1,970円 × 1,000株 = 1,970,000円
休日等で課税時期に終値がない場合の取扱い
課税時期が取引所の休業日に当たり終値が存在しない場合は、課税時期の前日以前または翌日以後で最も近い取引日の終値を課税時期の終値とみなします。等距離で前後が同じ場合は、その両日の終値の平均を用います。
留意点
・月平均の採用は「課税時期の属する月・前月・前々月」に限定します。相続後の月平均は比較対象に含めません。
・評価に用いた日付と数値は、証券会社または証券取引所等の客観資料で整理し、相続税申告書に添付または提示できるように保全します。
③ 上場株式の注意点と実務上のリスク
上場株式を相続する際には、手続きが比較的明確である一方、実務上の注意点も少なくありません。特に次のような点に注意が必要です。
配当金の受領は名義人基準で管理されるが、相続人による未払配当の請求は可能
配当金は名義書換時点の名義人に支払われますが、相続発生後に発生した未払配当は、相続人が株主名簿管理人(多くは信託銀行)に所定書類を提出して請求できます。もっとも、多くの発行会社は定款で払渡開始日から3年の除斥期間を定めているため、早期の手続が必要です。
所在不明株主の特例に留意する
株式自体が時効で消滅する制度はありません。もっとも、所在不明株主に該当する場合は、通知が5年以上到達せず、かつ5年間配当金の支払を受けていないとき、発行会社は所定の手続により当該株式を売却できる特例があります。相続発生後に連絡不能とならないよう、名義書換と連絡先の整備を早期に行います。
評価額の変動リスク
相続後の株価変動によって、分割時に相続人間で不公平が生じるケースがあります。遺産分割協議時に「評価時点」を明確にしておくことが重要です。
これらのリスクは、手続きの遅延や書類の不備によって生じることが多く、弁護士のサポートを受けながら進めることで未然に防ぐことができます。
非上場株式を相続する場合の手続と評価方法
非上場株式を相続する場合、上場株式に比べて手続が複雑になります。市場価格が存在しないため、株式の評価を行うには会社の財務状況や配当実績などを基に専門的な計算が必要です。また、相続等の一般承継による取得は承認不要であり、承認の要否が問題となるのは譲渡(売買等)の場合です。ここでは、非上場株式の調査方法と評価の仕組み、そしてトラブルを防ぐための注意点を解説します。
① 非上場株式の調査と確認方法
まずは、相続財産の中に非上場株式が含まれているかを確認します。非上場株式は証券会社での管理が行われていないため、以下のような資料を基に調査します。
- 株券や株主名簿記載事項証明書
- 株主名簿(会社が保管)
- 出資契約書、投資契約書
- 過去の配当通知書や株主総会招集通知
これらの資料が見つからない場合は、会社に直接問い合わせを行います。譲渡制限株式(会社法107条)であっても、相続などの一般承継による取得は承認不要です。相続で株式を取得した相続人は、株主名簿の名義書換請求(会社法133条)を行い、相続を証する書面や必要事項(会社法施行規則22条)を添付して手続を進めます。取締役会等の承認が必要となるのは「譲渡(売買等)」の場合であり、相続に承認は求められません。名義書換に必要な書式・提出先は発行会社または株主名簿管理人の案内に従います。
また、故人が自ら設立した会社の株式(いわゆるオーナー株)を保有している場合には、経営権や議決権の継承も検討する必要があります。株式の数や議決権割合が会社経営の支配関係に直結するため、慎重な相続対応が不可欠です。
株券不発行の原則と株券電子化の区別
非上場会社は、会社法により株券不発行が原則です(定款で発行を定めた場合のみ株券を発行します)。上場会社については2009年の株券電子化により、株式は振替制度で一元管理されています。したがって、非上場株式の有無を確認する際は株券の現物の探索に偏らず、株主名簿の記載、株主名簿管理人への照会、登記事項証明書の確認を併用します。古い株券が見つかった場合でも、現行の権利関係は名簿記載と会社の管理に従うため、名義書換の要否や手順を発行会社または株主名簿管理人に確認します。
② 非上場株式の評価方法
非上場株式の相続税評価は、財産評価基本通達の枠組みに従い、会社規模や株主の関与度に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式(必要に応じ配当還元方式)を用います。M&Aの企業価値評価で用いられるDCF法やゴードン成長モデルは、相続税評価の標準方式には含めません。
類似業種比準方式
上場同業他社の配当金額・利益金額・純資産価額の各指標を基に比準値を算出し、対象会社の1株価額を評価します。事業規模区分や株主の支配関係に応じて比重や補正を適用します。業績が平準化されている会社に適します。
純資産価額方式
対象会社の資産・負債を評価通達に即して時価補正し、時価純資産額÷発行済株式数で1株価額を算出します。保有資産が厚い会社、清算価値に近い評価が妥当な局面で有用です。含み損益や簿外項目を洗い出した上で調整します。
併用方式
上記類似業種比準方式と純資産価額方式を所定のウエイトで按分して評価します。一般に中小法人で、資産性と収益性の双方を反映させる必要がある場合に選択します。ウエイトは会社規模や業種区分に応じた基準に従います。
配当還元方式(少数株主等の特例)
議決権の影響力が乏しい少数持株など一定の要件に該当する場合に、過去の配当実績から株価を逆算します。会社の実体価値や支配プレミアムは反映しません。適用要件の充足を事前に確認します。
これらの評価方法の選択は、会社の規模・業種・支配権の有無・事業承継の有無などを総合的に判断して行う必要があります。評価の誤りは相続税額だけでなく、遺産分割や経営権の調整にも影響を与えるため、専門家(税理士・弁護士)の関与が不可欠です。
③ 非上場株式の相続でトラブルになりやすい点
非上場株式の相続では、評価の難しさに加えて、相続人間や会社側との利害対立が生じやすいという特徴があります。代表的なトラブルには次のようなものがあります。
株式の評価額をめぐる争い
評価方法の選択によって株価が大きく変動するため、「評価が高すぎる」「安すぎる」といった不満が生じやすくなります。
議決権や経営権をめぐる対立
相続によって複数の相続人が株主となると、経営の意思決定が停滞するおそれがあります。代表取締役の選任や会社方針に関する意見の対立も少なくありません。
これらの問題は、相続手続きの段階で弁護士が関与することで防止できるケースが多いです。弁護士は、株式評価の妥当性を確認し、遺産分割協議書の内容を法的に整理したうえで、会社との調整も行うことができます。
非上場株式の承認拒否時の対応・価格決定申立て
譲渡制限株式で会社が相続に伴う名義書換に応じない場合、会社法に基づく救済があるため、まず買取手続の枠組みを整理します。会社が承認しないと決定したときは、会社または会社が指定する買取人が当該株式を「相当の価格」で買い取る義務を負います(会社法140条)。「相当の価格」は相続人と会社の協議で定めるのが原則です。協議で定まらないときは、会社の承認しない旨の通知が到達した日から20日以内に、地方裁判所へ売買価格決定の申立てを行います(会社法144条、会社非訟)。
承認手続が遅延している場合は、承認請求の催告を行い、会社の判断を明確化します。承認拒否の有無や理由、提示価格の根拠、相続人の保有目的(支配権の有無を含む)を記録化し、評価書・計数根拠を添付して交渉・申立てに備えます。
株式の相続は弁護士への早期相談が安心
株式の相続では、上場株式は手続が比較的標準化されている一方、非上場株式は評価方法の選択や議決権配分など検討事項が多く、遺産分割の設計が会社運営に直結します。相続(一般承継)による取得は承認不要であり、承認が問題となるのは譲渡(売買等)の場合です。評価・株主名簿の名義書換・相続税・会社対応を並行して進めるには、相続・会社法務双方に通じた実務対応が有効です。
当事務所は「非上場株式/会社の相続トラブル」のご相談を多数いただいており、相続と企業の観点から一貫対応が可能です。まずは状況と優先順位を整理し、最適な手順とスケジュールをご提案します。
ご相談は電話またはフォームで受け付けています。早期にご連絡いただければ、名義書換や会社承認の要否、評価の当てはめ方(税務評価と分割基準の切り分けを含む)など、初動での取りこぼしを防げます。
非上場株式の相続にお困りならご相談ください。
お困りではありませんか?