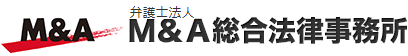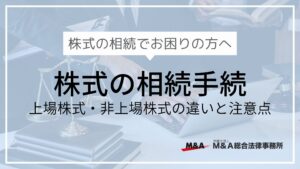事業承継税制とは?相続税や贈与税の負担を減らす仕組みや条件をわかりやすく解説
お困りではありませんか?

事業承継税制とは、会社を後継者に引き継ぐ際にかかる相続税や贈与税の負担を大幅に軽減できる制度です。条件を満たすことで、税金の支払いが猶予され、最終的に免除される可能性もあります。
中小企業の経営者で「後継者に事業を残したいけれど、税金の負担が大きい」という悩みを持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、事業承継税制の仕組みや条件、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。手続きの流れと注意点も紹介するので、最後まで読んで参考にしてください。
事業承継税制とは
事業承継税制とは、後継者に事業を引き継ぐときに発生する相続税や贈与税の負担を軽減するための税制優遇措置です。2009年の税制改正で創設されました。
通常、後継者が株式を取得すると多額の税金が発生し、資金繰りの悪化や株式売却による経営権の分散など、事業の継続に大きな支障が生じる可能性があります。事業承継税制を活用して一定の条件を満たせば納税が猶予され、実質的に税負担を抑えながら円滑な承継が可能です。
この制度には、一般措置と特例措置の2種類があります。特例措置は平成30年度の税制改正で導入されたもので、対象株式の上限撤廃や対象者の拡大など、より使いやすい仕組みになっています。ただし、適用を受けるためには「都道府県への計画提出」「雇用確保要件」など複数の条件を満たす必要があります。
事業承継税制は、単なる節税制度ではなく「後継者が安心して経営を引き継ぐための支援制度」であることがポイントです。中小企業の存続や地域経済の安定を守るためにも、多くの経営者が検討すべき重要な制度といえるでしょう。
事業承継税制には「相続税」と「贈与税」の2つが関係しています。どちらも条件を満たすことで、納税を猶予できます。
事業承継税制と相続税・贈与税の関係性
事業承継税制と相続税や贈与税の関係性を理解しておきましょう。事業承継の場面では、後継者が株式や資産を引き継ぐ際に「相続税」または「贈与税」が発生します。
中小企業オーナーにとっては、この税負担が事業継続を妨げる原因となります。そこで活用できるのが「事業承継税制」です。この制度を利用すれば、相続や贈与で取得した自社株式にかかる税額が大幅に軽減され、場合によっては納税が猶予・免除されることもあります。
中小企業では経営資源が株式に集中していることも多く、事業を引き継ぐときに後継者の負担になったり、資金繰りが難しくなったりしてしまいます。そのため、納税が猶予されれば、後継者の負担も少なく、資金を事業に集中して使いやすくなります。
相続税と贈与税で税率や控除額など違いがあるため、ここからは相続税と贈与税を分けて解説します。
相続税の場合
相続税は、被相続人から相続などで財産を受け取った人にかかる税金です。経営者が亡くなって後継者が会社を引き継ぐ場合、株式や不動産などの事業資産に対して相続税が課されます。
中小企業の株式は市場に流通していないため、現金化が難しい一方で、評価額は高く算定されやすい特徴があります。その結果、後継者は莫大な相続税を負担し、会社の資金を切り崩して納税しなければならないケースもあります。このような状況は、事業の存続を脅かす大きなリスクです。
事業承継税制を活用すれば、相続によって取得した株式にかかる相続税の納税が猶予され、一定条件を満たせば将来的に免除される可能性もあります。つまり、「後継者が資金繰りに追われて会社を手放す」といったリスクを避けられるため、相続税負担が大きい場合ほど、事業承継税制の有効性は高まります。
相続税は財産の取得金額が高くなるほど、相続税率も上がります。以下の表に、相続税率や控除額をまとめました。
| 法定相続分に応じた財産の取得金額 | 相続税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税の場合
贈与税とは、個人から財産を贈与された人にかかる税金です。経営者が生前に会社の株式や事業用資産を後継者に引き継ぐ場合、贈与税が発生します。
贈与による事業承継は、相続よりも早い段階で後継者に経営権を移せるメリットがあります。しかし、贈与税は相続税に比べて税率が高く設定されており、多額の納税負担が発生するのが大きなデメリットです。
事業承継税制を活用すれば、贈与により取得した自社株式にかかる贈与税の納税を猶予でき、後継者は経営資源を守りながらスムーズに事業を引き継ぐことができます。特に、贈与の場合は通常の税率が高いため、制度の利用効果がより大きく現れます。
「早期に経営権を移したいが、贈与税の負担が心配」という中小企業経営者にとって、事業承継税制は最も有効な選択肢となるでしょう。
贈与税率と控除額を以下の表にまとめました。
| 基礎控除後の財産の合計額 | 贈与税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
事業承継税制の仕組み
事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があります。どちらも事業を引き継ぐときの税負担を軽減するための制度です。対象や猶予率・利用できる期間に違いがあるため、それぞれ分けて解説します。
一般措置の概要
比較的広く適用できる基本的な制度です。特例措置ほど要件は厳しくありませんが、税負担の軽減効果は特例措置より小さくなります。
一般措置では、後継者が相続や贈与によって取得した株式などに対して、相続税や贈与税が猶予されます。ただし、特例措置と比べると猶予される額は少なくなっています。
| 対象株式 | 発行済議決権株式総数の2/3まで |
| 適用期間 | なし |
| 特例承継計画の提出 | 不要 |
| 納税猶予割合 | 相続100%
贈与80% |
| 後継者 | 後継経営者の1人 |
| 雇用確保要件 | 5年平均で相続・贈与時の80%以上を維持 |
特例措置の概要
特例措置は2027年12月末までの時限的制度で、条件を満たせば相続税・贈与税が最大100%猶予され、将来的に免除される可能性もあります。そのため、現時点での事業承継を検討している経営者にとっては、特例措置を活用できるかどうかが重要な判断ポイントとなります。
ただし、この制度を活用するには「特例承継計画」の提出が必要で、2024年3月末までに提出していなければ適用対象外となります。また、後継者が代表者に就任することや、雇用の維持などの要件も課されています。
事業承継税制の特例措置は、円滑な世代交代を後押しする強力な制度です。期限や要件を正しく理解して、計画的に準備を進める必要があります。
| 対象株式 | 全株式 |
| 適用期間 | 2027年12月31日 |
| 特例承継計画の提出 | 必要 |
| 納税猶予割合 | 100% |
| 後継者 | 持ち株10%以上の後継者3人まで |
| 雇用確保要件 | 実質撤廃 |
事業承継税制の条件
事業承継税制を利用するために必要な条件は、主に以下の4つです。
- 対象企業の条件
- 先代経営者の条件
- 後継者の条件
- 事業継続の条件
それぞれ詳しく解説します。
対象企業の条件
事業承継税制は、中小企業基本法に基づく中小企業が対象です。具体的には、資本金や従業員数が一定の基準を満たさなければなりません。
| 業種 | 資本金 | 従業員 |
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
先代経営者の条件
先代経営者の条件は、主に以下の2つです。
- 会社の代表者を務めていたこと
- 相続や贈与の前に筆頭株主または総議決権の過半数を保有していたこと
会社の代表者であるだけでなく、一族のなかで筆頭株主であることや、一族の保有する議決権と合わせて総議決権の過半数を保有している必要があります。また、贈与時に代表者の役職から降りていなければなりません。
後継者の条件
後継者にも条件があります。
- 後継者の選定:原則、事業承継のあとに会社の代表者にならなければなりません。
- 株式の保有:後継者が取得する株式の割合は、発行済株式の2/3以上が必要です。引き継いだ株式を一定期間(通常5年以上)保有し続ける必要があります。
- 経営継続:後継者が事業承継後、一定期間(通常5年間)にわたって経営に関わる必要があります。
後継者として会社を引き継ぐだけでなく、継続して代表者である必要があります。引き継ぎ後のことも考えた上で選定しましょう。また、後継者は状況によって複数人を選べることもあります。
事業継続の条件
事業継続も適用されるために必要な条件です。納税が猶予されるためには、5年間の継続が求められます。
- 後継者が会社の代表者であり続けること
- 受け継いだ株式を保有し続けること
- 相続・贈与時の雇用人数における8割を維持すること
条件を認められたとしても、代表者や保有株式など一定期間継続する必要があります。雇用条件については、日本の人手不足もあり条件が緩和されています。今までは、雇用の8割を満たせなかった時点で猶予は終了でした。しかし、現在では5年間の平均で8割を超えていれば条件が満たされるようになりました。
事業承継税制の特例措置のメリット
特例措置のメリットは主に以下のとおりです。
- 相続税や贈与税の納税が全額猶予される
- 最終的に税金が免除される
- 雇用の安定と企業の存続を支援できる
それぞれ解説します。
相続税や贈与税の納税が全額猶予される
後継者が取得する株式などにかかる相続税や贈与税が100%猶予されます。事業承継をすると、自社株の株価に応じた相続税や贈与税の納税義務が課されるため、納税の資金が大きな負担になりかねません。
特例措置を利用すれば、税金の支払いが一時的に免除されるため、後継者は負担が少なく事業を引き継げます。企業の資金繰りや後継者の負担軽減に繋がるため、経営資源が株式に集中している中小企業にとって大きなメリットといえるでしょう。
最終的に税金が免除される
特例措置を受け、後継者が一定期間の経営を続けるなど条件を満たした場合、猶予された相続税や贈与税が最終的に全額免除されます。
税金の猶予だけでなく、免除されれば資金繰りがかなり有利になります。これにより、将来の税金支払いの心配がなくなり、事業の発展や拡大に集中しやすくなるでしょう。
雇用の安定と企業の存続を支援できる
特例措置では、事業承継後の雇用維持が条件となっています。これにより、会社全体で雇用維持に取り組む姿勢が高まり、従業員の安心感も高まるでしょう。
従業員が大幅に減少することなく、安定した経営を続けることで企業の存続する可能性が高くなります。
事業承継税制の特例措置のデメリット
特例措置のデメリットは、主に以下のとおりです。
- 適用期限が決まっている
- 免除を受けるために一定の贈与などが必要になる
それぞれ解説します。
適用期限が決まっている
特例措置は適用期限が決まっています。2027年12月31日までに行われた相続や贈与でなければ特例措置の適用を受けられません。2028年以降は特例措置を受けられないため、期限には注意して早めに準備していきましょう。
特例措置を受けるためには、特例承継計画や認定申請が必要です。そのため、手続きに時間もかかります。手続きはスムーズに進められるようにスケジュール管理と準備は怠らないようにしましょう。
免除を受けるために一定の贈与などが必要になる
税額の猶予だけでなく、免除を受けるためには後継者が一定の贈与などをする必要があります。特例措置のいちばんの目的は納税の猶予ですが、一定の要件を満たせば納税を免除できます。
免除を受けるためには、原則として後継者が死亡する、または一定期間経過したあとに、次の後継者に事業承継税制の適用を受けるための贈与が必要です。納税の猶予と免除を受けるための要件は異なるため、注意しましょう。
事業承継税制の手続きの流れ(相続税の場合)
相続税における事業承継税制の手続きの流れは、主に以下のとおりです。
- 特例承継計画を作成する
- 相続開始後に都道府県庁へ認定申請をする
- 税務署への申告書を作成する
- 納税猶予
それぞれ詳しく解説します。
特例承継計画を作成する
事業承継税制の特例措置を受けるためには、特例承継計画の作成が必要です。
特例承継計画書の内容には、会社の事業内容や従業員などの基本情報から、承継前と承継後の経営計画を記載する必要があります。
計画書を作成したら都道府県知事に計画書を提出しましょう。必要な書類は、以下のとおりです。
- 確認申請書
- 履歴事項全部証明書
相続開始後に都道府県庁へ認定申請をする
2027年12月31日までに相続が発生した場合、特例措置が適用されます。
相続が開始されたら都道府県庁に認定申請をしましょう。期間は、相続が発生した日の翌日から8ヶ月以内に申請しなければなりません。
認定申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 認定申請書またはその写し
- 定款の写し
- 株主名簿の写し
- 履歴事項全部証明書
- 相続税に関する書類
- 従業員数証明書
- 相続認定申請基準事業年度の決算関係書類
- 相続開始後の上場会社または風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
- 特別子会社に関する誓約書
- 被相続人・相続人等の戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
- 特例承継計画またはその確認書
税務署への申告書を作成する
都道府県知事から認定をもらえたら、税務署に申告しましょう。
相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告期限までに、相続税の申告書と付随する書類を税務署に提出します。
納税猶予
書類の不備などがなければ、相続税の納税猶予期間に入ります。猶予期間も一定の条件を満たし続ける必要があります。
申請期限後の5年間は、都道府県庁へ年次報告書を税務署へ継続届出書を年1回提出しなければなりません。5年後からも、3年に1回は税務署へ継続届出書を提出する必要があります。
提出期限は必要書類も多くなってくるため、しっかり準備しておきましょう。
事業承継税制の手続きの流れ(贈与税の場合)
贈与税における事業承継税制の手続きの流れは、主に以下のとおりです。
- 特例承継計画を作成する
- 非上場株式などの贈与を行う
- 都道府県庁へ認定申請をする
- 納税猶予
それぞれ詳しく解説します。
特例承継計画を作成する
相続税の場合と同様に特例承継計画書の作成をして、都道府県知事へ提出しましょう。
非上場株式などの贈与を行う
贈与の場合、先代経営者等の贈与者から全部または一定数以上の非上場株式の贈与が必要です。
贈与に必要な株数は後継者の人数によって異なるため、必要な株数を事前に調べておきましょう。
都道府県庁へ認定申請をする
都道府県知事の認定を受けて、贈与税の申告期限までに税務署へ申告書や書類の提出を行います。
都道府県知事からの認定の申請は、贈与年の10月15日から翌年1月15日までに行いましょう。また、贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
相続税と期限が異なるため、注意しましょう。
納税猶予
納税猶予期間に入ってからも条件を満たす必要があります。
申告期限から5年以内の年次報告書や継続届出書を毎年提出します。贈与税の場合は、報告基準日が3月15日で、提出期限が6月15日です。
こちらも相続税と間違えないようにしましょう。
事業承継税制を活用するときの注意点
事業承継税制を活用するときの注意点は、主に以下の3つです。
-
適用要件を満たしているかの事前確認
-
制度利用後の継続要件とリスク管理
-
専門家による税務・法務のチェック体制
それぞれ詳しく解説します。
適用要件を満たしているかの事前確認
事業承継税制の適用を受けるには、厳密な条件があります。
承継する会社が中小企業基本法の定義に当てはまっていることや、後継者が一定割合以上の株式を取得して代表権を持っていることなどが求められます。また、都道府県への認定申請や税務署への届出も必要です。
要件を1つでも満たさなければ制度を利用できず、多額の相続税・贈与税を支払うリスクがあるため、条件を事前に確認しましょう。
制度利用後の継続要件とリスク管理
税制の特例措置を受けても、承継後に一定期間の事業継続が求められます。
例えば、特例措置では5年間の代表者継続や株式保有義務などが設定されています。この間に事業を廃止したり、株式を売却した場合には、猶予されていた税金が一括で課税される可能性があります。
事業承継税制は「承継後の経営を安定させること」が前提にあるため、長期的な経営計画を立て、途中で条件を崩さないよう注意が必要です。
専門家による税務・法務のチェック体制
事業承継税制は制度が複雑です。申請から承継後の管理まで多くの手続きが発生します。
経営者や後継者だけで独自に進めるのは難しいため、税理士や弁護士・事業承継に強い専門家への相談は必須です。専門家の助言を受けることで、必要書類の漏れや条件違反による適用取り消しなどのリスクを防ぐことができます。
事業承継税制は、税制改正によるルール変更も多いため、最新の情報を踏まえて正しく制度を活用することが大切です。
事業承継税制で専門家に相談すべきタイミング
事業承継税制で専門家に相談すべきタイミングは、主に以下のとおりです。
- 承継計画の作成時(要件を満たすか確認)
- 相続・贈与の発生前(期限管理のため)
- 雇用要件や株式要件を満たせるか不安な場合
それぞれ詳しく解説します。
承継計画の作成時(要件を満たすか確認)
事業承継税制を活用するには、事前に承継計画を作成して要件を満たしているか確認することが重要です。
計画書の作成は形式的な作業に見えますが、実際には「誰が後継者になるか」「株式をどのように承継するか」といった具体的な内容を盛り込む必要があります。内容を誤ると制度を利用できない可能性があります。
専門家に早い段階で相談することで、最適な承継スキームを設計できるでしょう。
相続・贈与の発生前(期限管理のため)
事業承継税制は、相続や贈与の発生前からの準備が不可欠です。制度の適用には一定の期限があります。
特に贈与の場合は、事前に都道府県への認定申請が必要で提出期限を逃すと適用できなくなります。相続発生前から税理士や弁護士に相談しておくことで、期限を守りながらスムーズに承継を進められます。
雇用要件や株式要件を満たせるか不安な場合
事業承継税制の特例では、雇用の維持や株式の保有割合など、厳しい要件を継続的に満たす必要があります。
特に中小企業の場合、業績の変動や人材の入れ替わりによって雇用要件を維持できないケースも少なくありません。また、株式要件についても、親族間での分散や議決権の割合に注意が必要です。
このような不安がある場合は、早めに専門家へ相談してリスクを把握しておきましょう。
まとめ
今回は、事業承継税制の仕組みや条件について解説しました。
事業承継税制は、中小企業の後継者が安心して経営を引き継ぐために設けられた強力な税制優遇措置です。事業承継税制を利用すれば、後継者の負担も少なくなり、資金も事業に充てられます。一定の条件を満たせば、納税の猶予だけでなく免除されることもあります。
相続税や贈与税の負担を大幅に抑えられる一方で、要件を満たさなければ適用できず、途中で条件を外れると大きなリスクを伴います。
事業承継を検討する際は、早めに専門家へ相談し、最適なスキームを設計しておくことが成功への近道です。事業を引き継いだあとに、スムーズな経営ができるようにするためにも事業承継税制を理解しておきましょう。
お困りではありませんか?